「遊んでばかりで大丈夫?」——小学校高学年になると、受験や成績への不安から、そう感じる保護者も少なくありません。確かに、テストで点を取るには、ある程度の演習量や知識の定着が必要です。しかし、だからといって遊びを削ることが、必ずしも学力向上につながるわけではありません。
実は、遊びの中で育まれる力こそが、学びの質を高め、結果としてテストの点にも反映される土台になります。例えば、戦略的なボードゲームや創作活動では、論理的思考力や集中力、問題解決力が自然と鍛えられます。これらは、算数の文章題や理科の実験問題など、思考力を問われる場面で大きな力になります。
また、遊びの中で「自分で考えて行動する」経験を重ねることで、学習にも主体的に取り組む姿勢が育ちます。自分の行動が結果につながるという効力感や、取り組みに対する自己評価が高まることで、学びへの意欲が持続しやすくなるのです。
では、大人はどのように関わればよいのでしょうか。まずは、学びの場面でも「遊びのような充足感」が得られるようにすること。例えば、問題を解くときに「どうやって考えたの?」と過程に注目したり、「自分で解き方を工夫してみよう」と選択の余地を与えたりすることで、子供の主体性を引き出すことができます。
さらに、学習の成果を子供自身が実感できるようにすることも大切です。「前より速く解けたね」「自分で気づいたのがすごいね」といった声かけは、自己評価を高め、次の学びへの意欲につながります。
遊びを削って学びを詰め込むのではなく、遊びの中で育まれる力を学びに活かす視点が、これからの教育には求められています。大人の関わり方ひとつで、子供の学びは深まり、結果としてテストの点にもつながるのです。
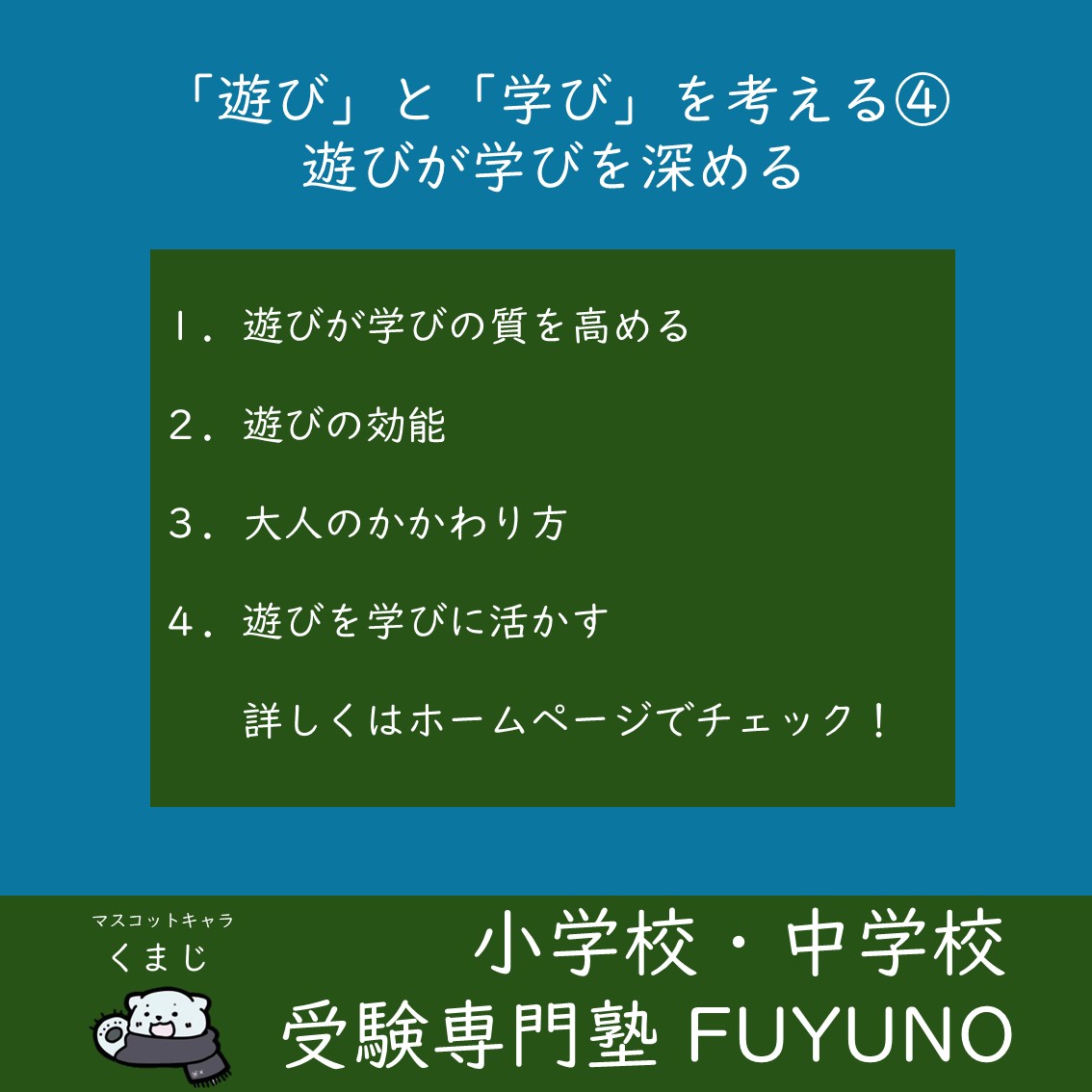
コメントを残す