「プログラミング的思考って大事そうだけど、どうやって育てるの?」という疑問にお答えするのが、今回のテーマです。FUYUNO塾では、年中さんから小学生まで、発達段階に応じて「考える力」を育てる取り組みを行っています。
たとえば、年中さんには「順序立てて考える」遊びを取り入れます。「おやつを食べるにはどうする?」という問いに、「手を洗う→お皿を出す→座る→食べる」と順番を考える。これだけでも立派な思考力のトレーニングです。年長さんになると、「もし〜だったらどうする?」という条件分岐の考え方を遊びの中に取り入れます。「雨が降ったら傘を持つ」「晴れなら帽子をかぶる」といった具合です。
さらに、FUYUNO塾ではAlilo(アリロ)というロボット教材や、思考力育成アプリ「シンク・シンク」なども活用しています。これらの教材では、子どもたちが自分で考え、試して、うまくいかなかったらまたやり直すという試行錯誤のプロセスが自然に生まれます。失敗しても、もう一度挑戦する。まずはやってみる。こうした姿勢そのものが、広い意味での「プログラミング的思考」だと私たちは考えています。
小学生になると、より抽象的な思考にも挑戦します。算数の文章題を解くとき、「何を聞かれているか」「どんな情報があるか」「どんな順番で考えるか」を整理する力が必要です。これはまさに、プログラミング的思考の応用です。問題を分解し、必要な情報を抽出し、順序立てて処理する——この力があると、算数だけでなく、国語や理科にも強くなっていきます。
FUYUNO塾では、こうした思考力を育てるために、小さな挑戦の機会をたくさん用意しています。子どもたちは、遊びの中で自然と「考える力」を身につけ、気づけば算数の問題にも強くなっている。そんな学びの場を、これからも提供していきたいと思っています。
次回は、家庭でもできる「プログラミング的思考」の育て方についてご紹介します。
🔜次回予告(第3回)
家庭でもできる!「プログラミング的思考」を育てる声かけや遊びの工夫をご紹介します。
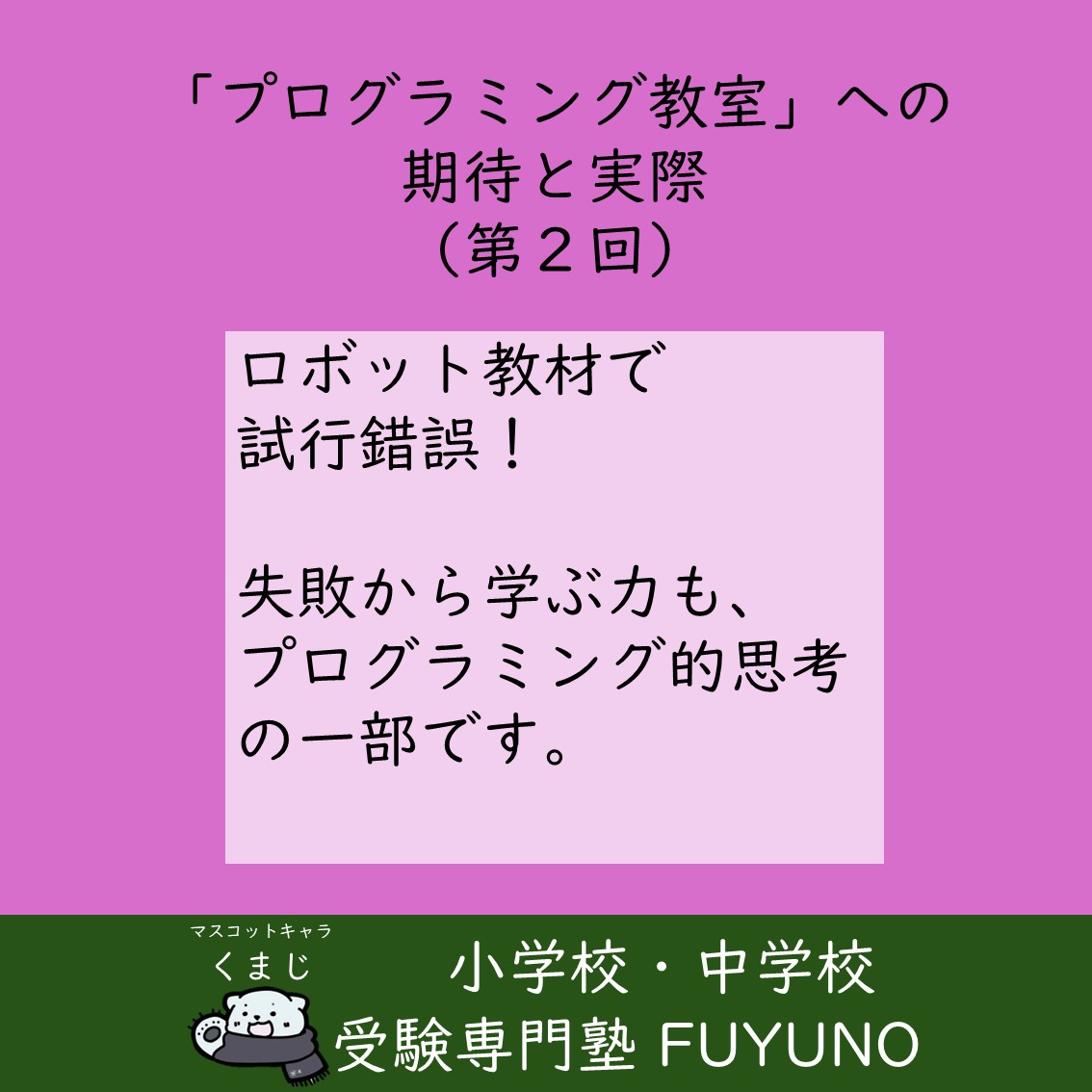
コメントを残す