「プログラミング的思考」という言葉、聞いたことはあるけれど、実際にどんな力なのかはよくわからない——そんな保護者の方も多いのではないでしょうか。今回は、この「プログラミング的思考」の正体について、少し掘り下げてみたいと思います。
まず、プログラミング的思考とは、物事を順序立てて考えたり、条件に応じて判断したり、複雑な問題を分解して整理したりする力のことです。たとえば、「朝起きてから学校に行くまでの流れを説明してみて」と言われたとき、子どもが「起きる→顔を洗う→朝ごはんを食べる→着替える→ランドセルを背負う→出発する」と順序立てて話せるなら、それは立派なプログラミング的思考の一例です。
この力は、プログラミングのコードを書くときに必要なだけでなく、算数の文章題を解くときや、国語で登場人物の気持ちを整理するときにも活きてくる、とても汎用性の高い思考力です。つまり、教科を超えて「考える力の土台」となるものなのです。
小学校では、フローチャートやブロック形式のプログラムを使って、この思考を育てようとしていますが、前回お伝えしたように、授業の頻度は年に1回程度。しかも、教える側がこの思考法をしっかり理解していないと、ただの「操作の時間」で終わってしまうことも少なくありません。
だからこそ、「プログラミング的思考」を育てるには、専門的な理解を持った指導者と、子どもが実感を持って取り組める教材、そして十分な時間が必要なのです。これは、コードが書ける人が教えれば自然に育つ、というものではありません。
FUYUNO塾では、年中さんからこの「考える力」を段階的に育てています。子どもたちは、遊びの中で自然と「順序」「条件」「繰り返し」といった考え方に触れ、気づけば算数の問題にも強くなっている。そんな学びの仕掛けを、日々の授業に組み込んでいます。
次回は、実際にどんな教材や活動を通して「プログラミング的思考」を育てているのか、FUYUNO塾の実践をご紹介します。
🔜次回予告(第2回)
FUYUNO塾では、どうやって「プログラミング的思考」を育てているの?年中さんからの実践例をご紹介します。
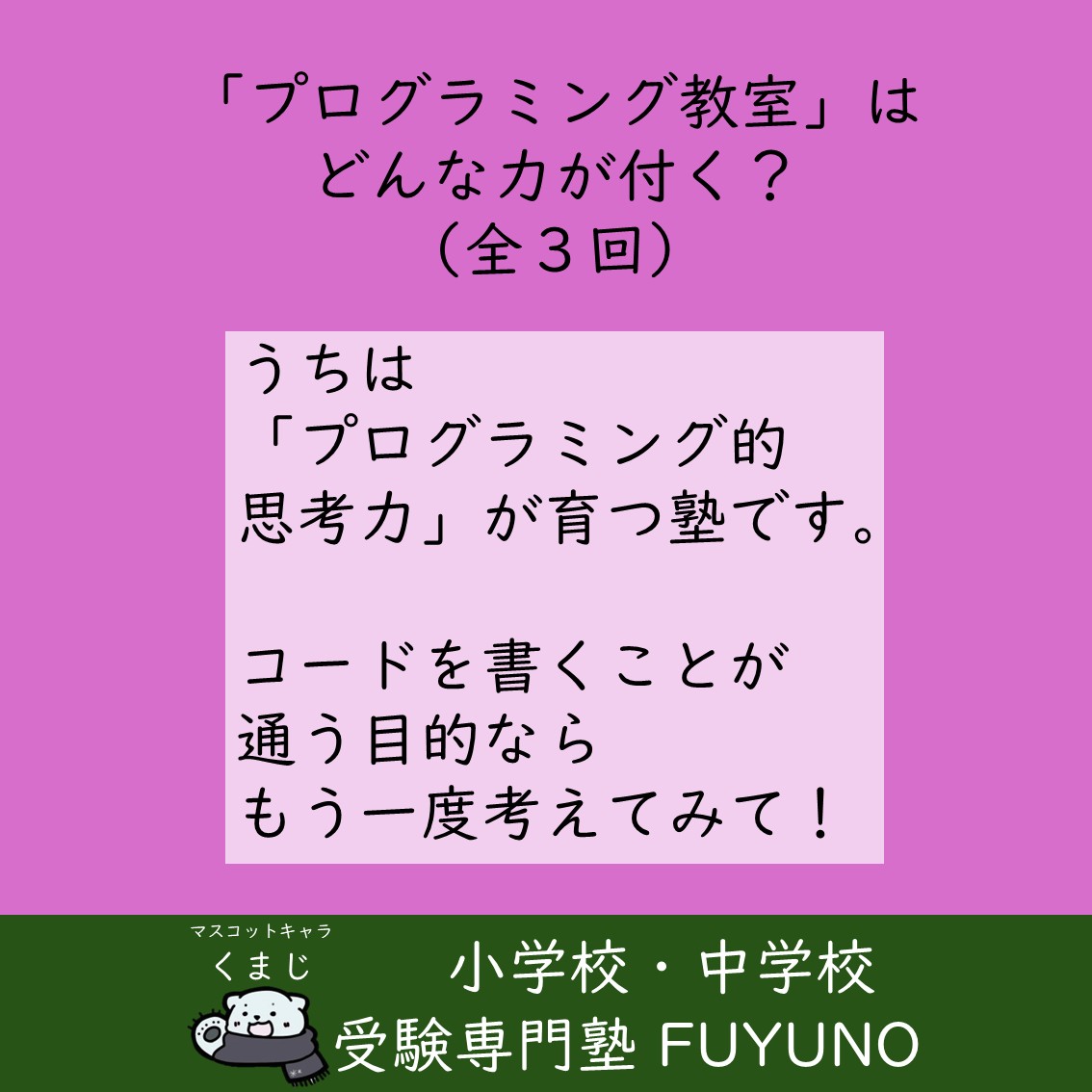
コメントを残す