願書文を書くとき、「何を書けばいいのか分からない」と悩む方は少なくありません。
その原因のひとつが、“具体性”の不足です。抽象的な言葉だけでは、子どもの姿や家庭の思いが伝わりにくくなってしまいます。
たとえば、「優しい子です」と書かれていても、読み手にはその優しさがどんな場面で表れたのかが分かりません。
それよりも、「妹が泣いていたときに、黙って隣に座って背中をさすっていた姿に、優しさを感じました」と書けば、情景が浮かび、子どもの性格が伝わります。
具体性とは、場面・行動・気持ちの3つがそろっていること。
「どんな場面で」「どんな行動をして」「そのときどう感じたか」を書くことで、願書文はぐっと読みやすく、印象に残るものになります。
また、具体的なエピソードを書くことで、家庭の関わり方も自然と伝わります。
「朝の支度を自分でできるようになった」だけでなく、「最初は声かけが必要だったけれど、今は時計を見ながら自分で動けるようになった」と書けば、成長の過程と家庭の支えが見えてきます。
願書文は、子どもの“今”を切り取るもの。
だからこそ、抽象的な言葉よりも、日常の中の小さな場面を丁寧に描くことが、読み手の心に届く文章につながります。
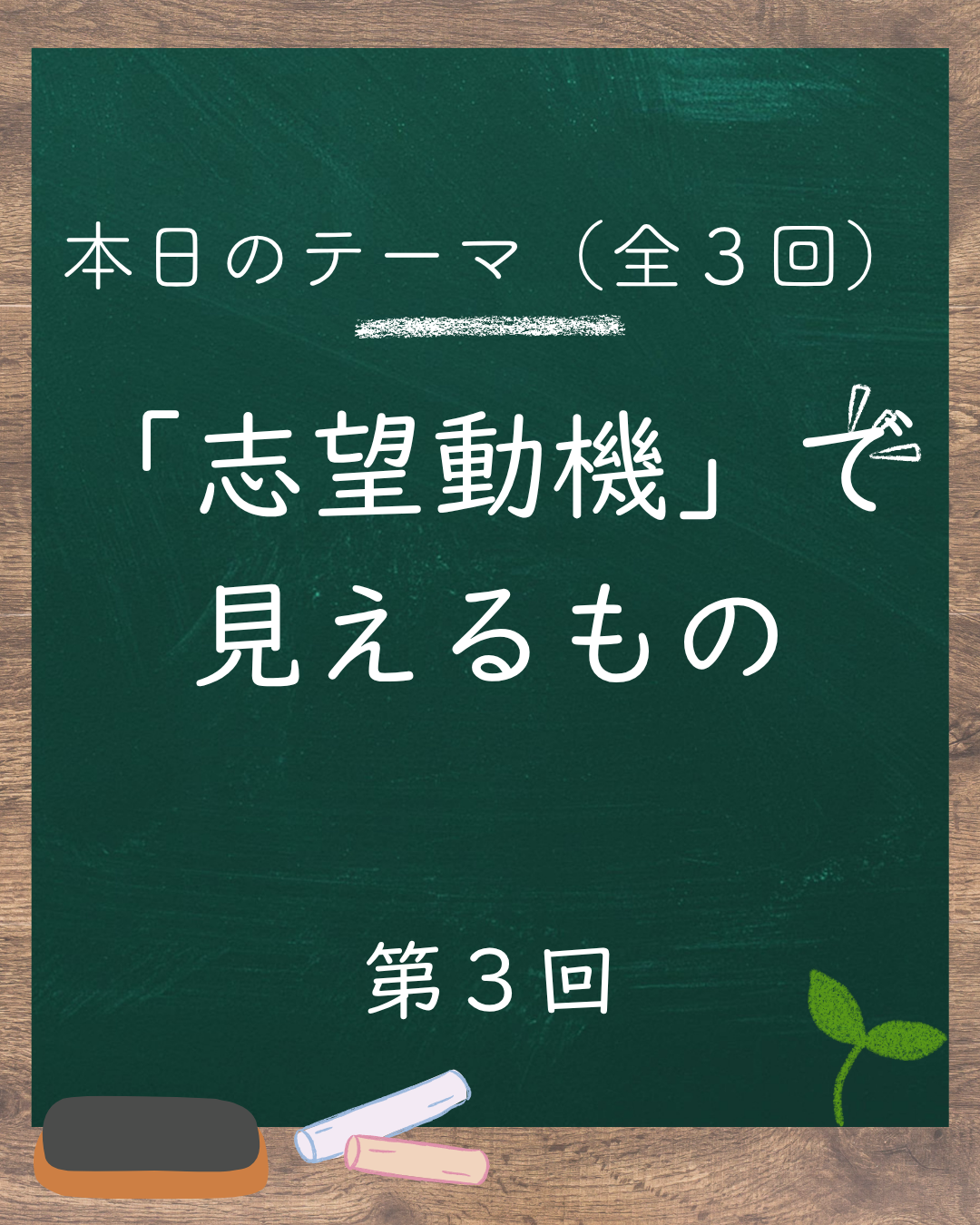
コメントを残す