似ているようでちがうこの2冊。
そもそも対象が違います。子育て本は家庭向け。よく買うのはお母さん方ですね。学校の先生は基本、あまり読みません。逆に教育専門書の対象は学校の先生。こちらの本は各ご家庭の方が手に取ることはほぼないでしょう。
子育て本のことをあまり悪く言うつもりはないのですが、多くの本が「煽り文句」や「キャッチーなタイトル」がついています。売れてなんぼの商業本ですから、仕方ないとは思います。個人の感想や経験が、普遍的な事実のように一般化されて語られることもあります。もちろん、いい本もたくさんありますが、「本当にそうなの?」ということについての検証は、もっとあったらいいなと個人的には思っています。
一方で教育専門書は、「どうしたらよい指導ができるか」のような内容ですから、かなり向上心のある、かつ時間を生み出せるような先生でないと読めない、読まない本です。ただし、裏付けは論文だけでなく、国家レベル(例:文部科学省、OECD等)の検証がされている、お金も時間も手間もかかっているものが多いです。ただ、「目の前の子供たちに当てはまるのか?」ということを頭の片隅に置かないと、頭でっかちの指導論になってしまいがちです。
両者を比べると、子育て本は、商業本は「売れやすい・ウケやすい」ノウハウが詰め込まれているので、読みやすくて、(一見)わかりやすい。教育専門書は、「専門的で難しいことを言っている」、机上の空論過ぎて「あまり信用できない…」というところがあるのではないでしょうか。さらに専門書は内容的にもハードルが高い。
自分は教員としての歴が長いので、教育専門書ばかりを読んでいました。しかし最近になって、子育て本もかなり読むようになりました。そして、両者には、もっと決定的な違いがあることに気付きました。
それは、子供にかけられる時間的制約の捉えです。
子育てにおいては、相手は基本わが子・1人(+きょうだい)です。子供とどう係わればいいのかについて、(教育現場と比較して)時間的制約を比較的緩やかにとらえています。
学校教育においては、「待つ・聞く」などの姿勢が大事という基本的なことは変わりませんが、何せ同時に30人以上を同時に相手にする必要があります。上記のスタイルの程度には限界があるわけです。Aさんの話をゆっくり聞いている間に、「他の29人は待っててね」なんてことは現実的にできないわけです。ただ、「先生」というのは学校教育のプロですから、スピードと待つ姿勢のベストバランスを探りながら進めます。
子供にかけられる時間的制約において、子育て本と教育専門書の中間くらいにあるのが、「特別な支援が必要な子供」関連の本です(これも広く言えば教育専門書ですが、小カテゴリとして紹介します)。
こちらは、野原先生が専門になりますが、ADHDやASD(自閉症スペクトラム障害)の子供たちとの関わり方について書かれた本です。専門家の先生が、少人数の子供たちとのよりよい関わりについて書かれていたりします。家庭教育よりは忙しいけど、30人学級よりはゆるやか、という感じでしょうか。
学校の中では、特別支援学級と通常級(わかりやすくするため便宜上こう書きます)の先生同士で、子供の関わり方について意見がぶつかることがあります。よくよく聞いていくと、双方の「時間的制約」の感覚の違いに起因するものであることが多々あります。
上の例で考えると、特別支援学級の先生も、通常級の先生も、言っていることは正しいのだけれど、相手(子供)の数が違うことで、最適解(ベストの係わり方)がかわる、ということになります。これはもちろん、家庭教育と学校教育でも、(同じ「教育」でありながら)違いが出てくるということです。
長い前置きになりました。「子供を育てる」という大きな文脈において、様々なその場に応じたスキルを得るためには、それぞれの立場への理解と共感、そして自分の立場における応用が必要でしょう。
そのためには、子供を育てる本(子育て本、教育専門書)の垣根を越えて、それらに触れられる場所が大事だと考えています。当塾の午前中に開かれる「Ring」のセミナーやサロンでは、これらのことがテーマになります。そのための本は、塾の後ろにたくさん並べたいと思っています(ストックは合計100冊以上あります)。
その本棚がそろそろ届くということで、こんな記事を書いてみました。それらの本に興味を持った方がいたら、貸し出しも致しますので、ぜひいらしてほしいと思います。本棚が納品され、本が納められたら、再度ご案内します。
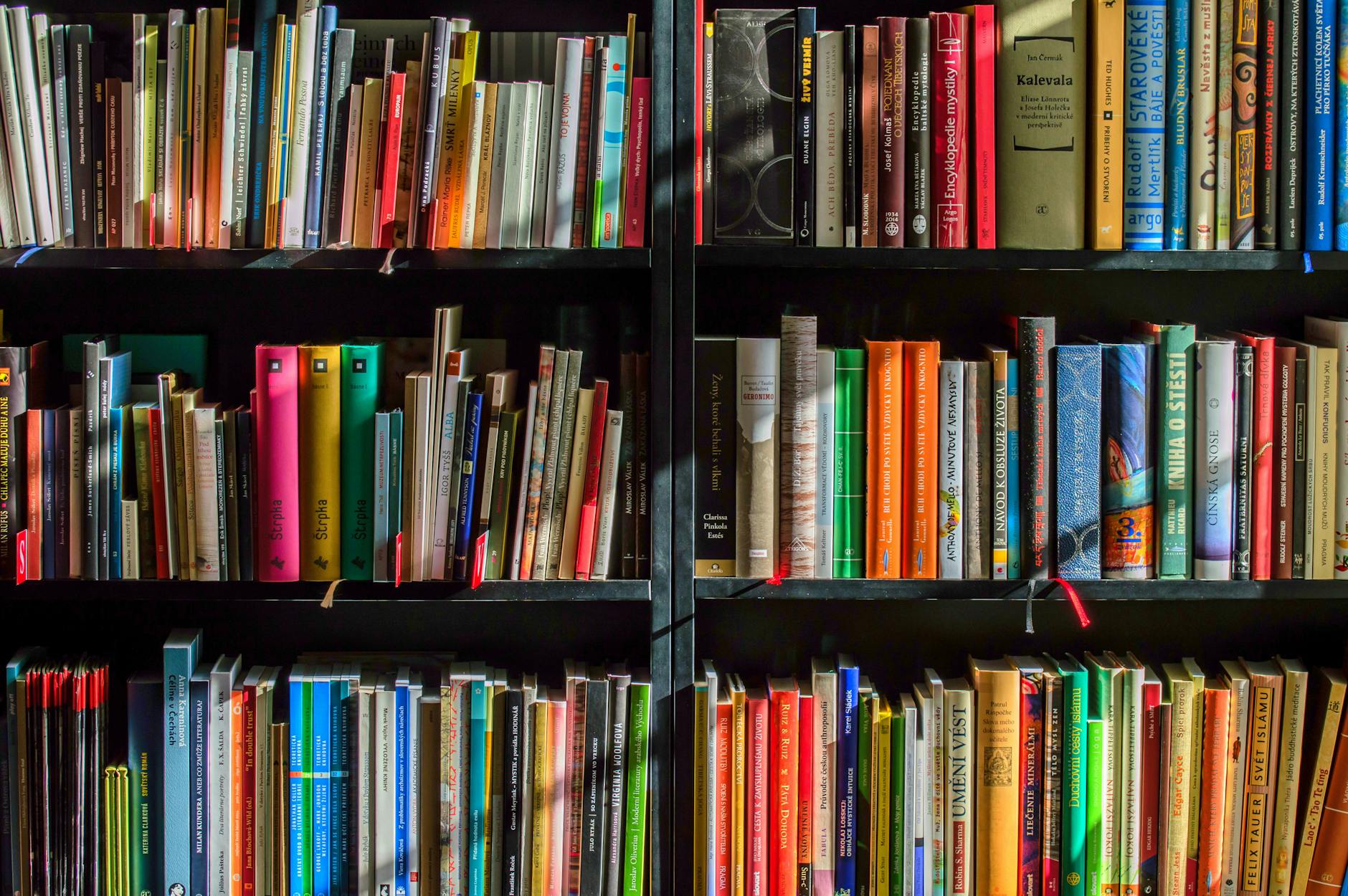
コメントを残す