仕事柄、いわゆる早期教育や幼児教育、塾のキャッチフレーズなどをよく見るのですが、よく「思考力を育む」というフレーズを見かけます。はたして、一般的には抽象度の高い「思考力」という能力は、いったいどういうものなのでしょうか。また、それを育てるにはどうするのがよいのでしょう。
みなさんは「思考力が高い子供」と言われると、どんな姿を想像するでしょうか。論理立てて(時に少し理屈っぽく)、よく話す子供を想像するのではないでしょうか。あるいは、ずっとに考えていることを書いている姿を想像するかもしれません。何となく、行動派のいたずら好きの男の子のイメージがあるのは私だけでしょうか。
実は、「思考力」は学習指導要領の中で、ある程度定義されています。育成を目指す資質・能力の1つとして、「思考力・判断力・表現力」とまとめられています(あと2つは「知識・技能」「学びに向かう力、人間性)。ここで、「思考力・判断力・表現力」について分析的に見てみましょう。
この3つは、同じカテゴリーでまとめられているものの、一括して「思考力」と言っているわけではないですから、別々のものと考えられます。しかし、これらを一体に捉えているということは、(「知識・技能」がそうであるように)有機的なつながりがあり、互いを補完し合うものと考えられているということになります。
つまり、「思考力」は単一で存在するものではなく、「判断力」「表現力」と一体的に育成を目指すものということです。
少し専門的な話になりますが、この場合注意した方がよいのは、中黒(・)でまとめられるこれらの用語(今回は「思考力・判断力・表現力」)は、一つ一つの言葉が何を指しているかを理解することにはそれほど意味はなく、それらを一体的に捉えることが大事であるということです。(例:「資質・能力」)
学習指導要領では、思考すること、判断すること、表現することを一体的に捉えているということですから、「思考力」を育てるには、判断や表現する場面を多く設定し、主体的に学ぶ環境づくりが重要ということになります。先の「思考力が高い子供」の姿と重なる部分があるのではないでしょうか。つまり彼らは「(判断しながら)表現をする子供」と言い換えることができるでしょう。逆に言えば、頭の中だけで完結したものは、本当の意味で「思考力」が育っているとは言えないということです。
「思考力」を育てるために私たち大人ができることは、子供が安心して表現できる環境を作り、表現を認めてあげることです。逆にやってはいけないのは、子供の行動を先回りし、表現をする機会を奪うことです。
「そんなことをしては危ないよ」「失敗するからやめなさい」「こうしたほうがいいんじゃないの?」。親心から心配する気持ちはよくわかります。しかしそれは、子供の好奇心ではなく親の機嫌を伺わせ、安心して追求する場を奪っている行為とも言えてしまうのです。これでは「思考力」は育ちません。
子供の思考力を育てるために必要なのは、「思考力を育てる問題集」ではありません。子供が興味をもったことに取り組むとき、「大人の覚悟」「失敗する時間の保障」「子供を認める声がけ」ができるかにかかっていると言えます。特に幼児~小学校低学年の時期に、失敗させる場面をどれだけ作れるか。そう言い換えても良いかもしれません。
参考:子どもに教えるときにほんとうに大切なこと 田中博史先生
~以下 私的な「思い」の話
それを本来は「算数の授業」の中でするのです。計算を間違い、立式を間違い、話し合いで間違いに気付く。だから学校は「間違えていい場所」ですし、効率的に知識注入しないからこそ、授業時間にゆとりがある。逆に一般的な塾では、効率的なことをするから一週間にたった1回の授業で、学校の授業の内容を「できるようにする」ことは可能なのです。
「思考力」を育てる授業を、あえて塾でもする。もちろん「思考力を育てる問題集」とやらに頼るのではなく、週にたった1(~2)時間の授業で。これはFUYUNOにとっては大きな挑戦であり、学校での学びとセットにして「算数を楽しみながら(思考)力をつける」ことこそが、この塾で目指す子供の姿です。
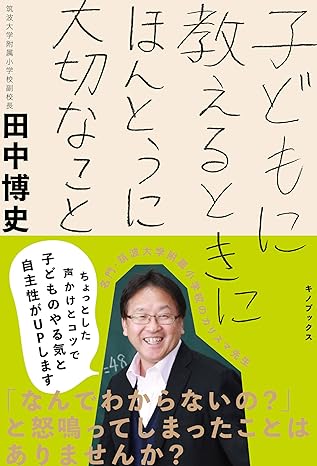
コメントを残す