世の中には一定数、権力的なものに対してその本質を見ることなく、自らの経験に基づいて批判する人がいます。特に幼児教育・学校教育は日本国民のほとんどが経験し、「プレイヤー」だった時期がある分野です。何となくその世界について、「大部分を知った気になり」「事実ではないことを勘違いし」「本来の意味とは違う解釈をして」「(既にずっと発信されていることを)新しい発見をした気になる」ことが起こりがちです。
大人として「学ぶ子供」を育てるために、「謙虚な学習者」の姿であることは大事だと考えますが、思い込みや勘違いは、真実・事実がないと新しい知識として更新することは難しいので、そういった内容を発信し、大人は「主体的な学習者(アクティブ・ラーナー)」になって子供にいい教育環境を用意できるようになろうというのが本記事の趣旨です。今回は初等教育(小学校・中学校)編。
最近、Instagramで「実は!算数の本質は『論理的に考えることであり、計算ではない』のです。」といった内容の投稿を見ました。その投稿のコメントには、「そうだったのか!」「教えてくれてありがとう」「今の学校教育は間違っている」「先生方はこういう授業をしてほしい」といったものがあふれていました。
なるほど。「昔(コメントをしている人の子供時代)も今(今の子供)も算数は計算だと思われていて、論理的思考の大切さは伝わっていないのか」と考えさせられます。そして、「多くの学校の先生方は何を指針にして算数の授業をしているのか」と言うことに思いを馳せました。
私の教員時代(約25年前~2年前)は、熱心な先生方もいればそうでもない先生方もたくさんいました。一生懸命な先生方は、「教科書を教えるのではなく、教科書で(本質を)教えるのだ」というのが口癖でした。一生懸命でもない先生方も、「教員採用試験」を合格した方々です。教員採用試験では、「学習指導要領」という学校教育における指針が示されている内容を、学んでいたはずです。
この「学習指導要領」は、正直その気になれば教員採用試験以降は、一切目にしなくても授業をすることはできます。なぜなら、教科書がその「学習指導要領」の内容に準拠して作られているからです。「教科書を教え」れば、意識の有無関係なしに、学習指導要領の趣旨に沿って一通り教えていることになります。
また、反体制側も多い教員の世界では、学習指導要領を目の敵にする人がいたり、不勉強ゆえに「あんな物は価値がない」といわゆる「酸っぱい葡萄」を決め込んだり、前述の「(旧来の)学校批判体勢」から否定的な感情をもっている人が一定数います。最後の「学校体制批判」は、教育専門外の方にも多くある感情でもあると思います。まれに見かける「学習指導要領にガチガチに縛られた教育は…」や「教員は学習指導要領の内容だけ教えていればいい」なんて表現する人は、まず間違いなく読んでいません。別に、教育専門外の人も「全員が学習指導要領を読もう」なんて言うつもりはありません。少なくとも教育に係わる人は、まずは国が出している方針に触れて、フラットな状態でそれについて考える姿勢をもってほしいと思うのです(専門で関わるなら、良い授業をするためにしっかり読むべきだと思います)。
さて、冒頭の話に戻ります。ここで改めて「なぜ算数を学ぶのか」を国(便宜的に、文部科学省「学習指導要領」とします)はどのように提示しているか確認しましょう。
【算数編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説より「算数科の目標」を引用
数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通して,数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1)数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに,日常の事象を数理的に処理する技能を身に付けるようにする。
(2)日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力,基礎的・基本的な数量や図形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力,数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じて柔軟に表したりする力を養う。
(3)数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き,学習を振り返ってよりよく問題解決しようとする態度,算数で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養う
少しだけ専門的な話をするならば、この学習指導要領に改定されたときに、他の教科等との整合性を図るために、このような書き方になったという経緯があります。以前の算数科の目標が色濃く残っているのは、この中で言えば(2)の内容です。特にこの部分、
日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力
算数は、「考察する力」を育てる教科であると記されています。ちなみに中学校の学習指導要領(数学)では、同じく算数科の目標(2)において、こうなります。
数学を活用して事象を論理的に考察する力
「筋道立てて」→「論理的に」と発展するということです。教科の系統性を考え、一般的な用語に落とし込むのであれば、つまり算数もまた「論理的思考力」を育てる教科と言えます。
さてもう一度冒頭の話に戻って、コメントがどんな様子だったか思い出してみます。教師だった立場から思えば、その動画を見て「そうだったのか!」と言わせてしまったのでは、「算数の目標」は伝わらない授業をしていたということになると考えます。得意気に「算数は論理を育てる教科なのです!」と話しているその人も、「車輪の再発明」をしただけであり、その人にも伝わっていません。
学習指導要領の趣旨に沿って授業をしている熱心な先生方、学習指導要領の内容を作り上げた方々、そしてまた新学習指導要領を作っている方々においては、言いたいことがたくさんある動画だと思います。でも、そういった人たちは、そもそもそんな動画を見ていないか、言っている時間があったら、目の前の仕事に打ち込むかしているのだと思います。
私は教育を専門的に扱う仕事を、一般的な教員よりは多く見てきたつもりです。その中で、「国家レベルでお金を投じ」「世界との比較をし」「国レベルでの経年変化を見取って」「実践家を中心とした全国の有識者が参加して」「歴史的に全世界レベルで最高レベルである国の」方針(≒学習指導要領)が、現在の社会の中であまりに評価されていないこと、指針とする気も学ぶ気もない「(自称)教育関係機関」が多いことに、とても危機感をもっています。例えるなら、医者を否定して民間療法を妄信するようなものです。今の教育界隈には、想像以上に「これやってみたらウケがいいかも」「これをやったらうまくいった」という個人の思い付きやたった一人の経験則・ライフハックと同等レベルの「先進教育」がたくさんあります。
子供への教育においては、「何となくいい感じがする」「今風で新しい」などのフワフワした価値観ではなく、根拠のある信念をもって行われている環境を準備したいものです。
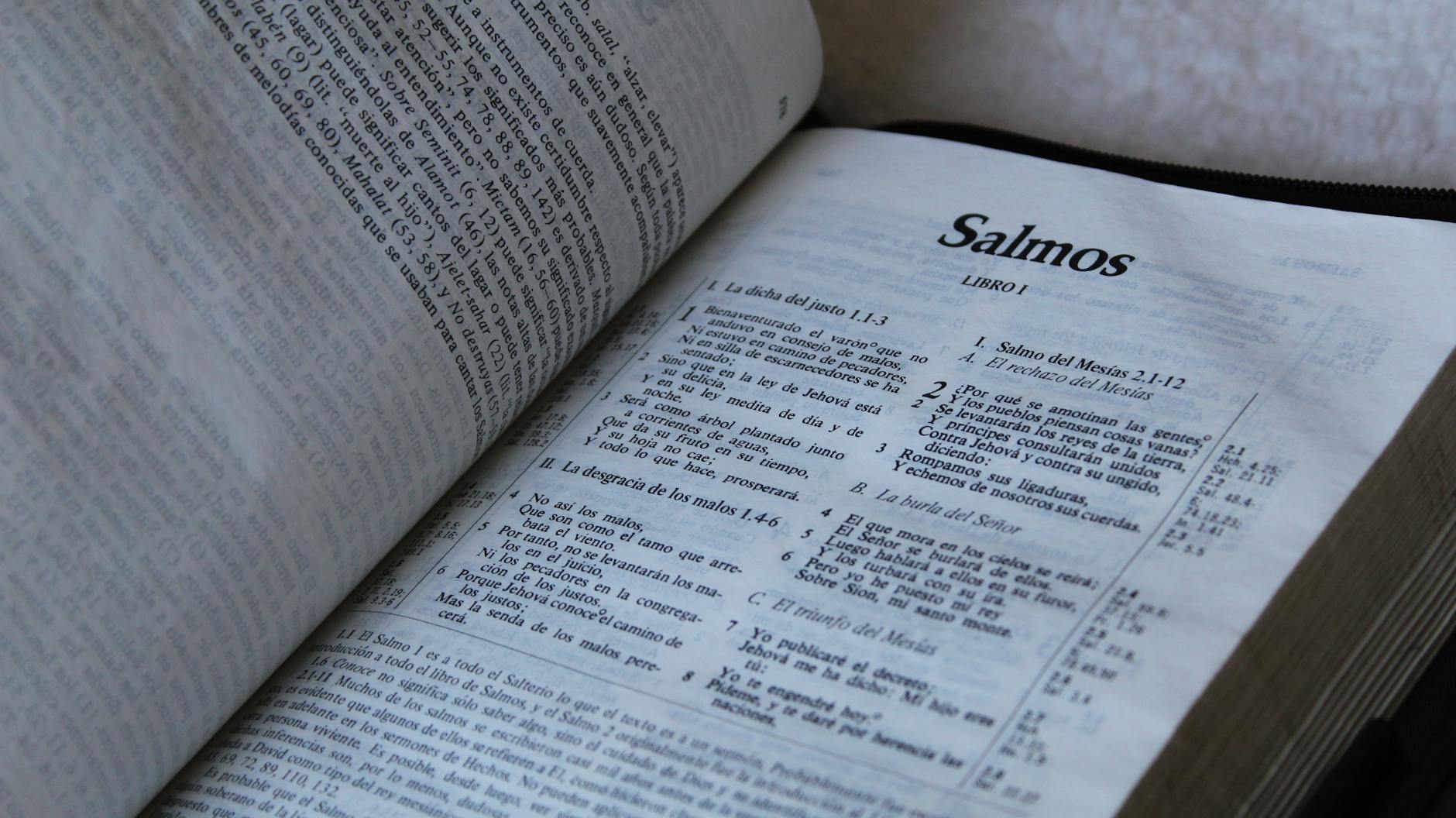
コメントを残す