前回記事はこちら。
(1)を踏まえ、具体的な判断基準を示していくのが本記事です。
② 「よい問題集」は、子供によって違う
子供が問題を解けるようになるには、いくつかの細かなステップがあります。まずは、それぞれの段階を明確にしていきましょう。
A. 問題の意味が分かる(読解)
B. 経験的に類推し、解法が浮かんでいる(知識・技能)
C. 論理的に解決できる道筋ができている(思考・表現)
D. いつでも思い出せる(関心・意欲・態度)
往々にして「解き方」ばかりに注目し、B.の段階だけで学習を進めようとする保護者や子供をよく見かけます。具体的には「『あわせて』は『たし算』だよ」、「『はじきの図』に当てはめて~」などです。考えることが難しい場合や、学習の初期段階では否定しませんが、C.やD.の力を育てるうえでは妨げとなる可能性があります。
よくある子供の考え方の例は、「今は『かけざん』の学習だから、かけ算の式を作ればいい」、「公式を覚えて、それに当てはめれば答えが出る」などの思考です。このような学習スタイルの子供は、事象のイメージができておらず(=「概念」として理解できていないため)、別の単元に進んだときに、どう考えればよいか分からなくなってしまいます。
余談(マッチョイズム)
その結果、勉強を「やりすごすもの」や「義務としてこなすもの」として捉えてしまう子供も少なくありません。こうした背景には、「苦労しなければ成果は得られない」といった勤勉主義的な価値観(いわゆる“マッチョイズム”)が影響していることがあります。実はこの考え方は、大人(先生や保護者)自身が経験から無意識に抱いていることも多く、知らず知らずのうちに子供に「苦労そのもの」を求めるような指導になってしまうこともあります。
さて本記事では、「子供によって違う」ことを強調していますが、これは「子供を理解したうえで、問題集を選びましょう」という意味合いが強くあります。問題集を解くのは子供であり、その子供の特性を理解せずに課題だけ与えても、保護者の期待は達成されないことの方が多いです。
ただ、実は小学生期の子供は、「問題集選び」に影響を与えるような「個性」は限定的といえます。例を挙げると…
視点1 コツコツ型 or 気分屋タイプ
視点2 ポジティブ(自信家) or ネガティブ(控え目)
視点3 聞いて覚える or 見て覚える or 書いて覚える
視点4 学習習慣あり or なし
特に問題集選びにおいて、視点1は大きいです。自分の子供はどのタイプで、それに「合う問題集を選ぶ」という考え方が大切です。記事1に書いたように、親がゴールを決め、「中学受験するなら、みんなこの問題集をやっているから」などと選ぶのではなく、身近な専門家に相談するのが望ましいです。
以上を踏まえ、具体的な目標を設定してそれに近い選び方をすれば、失敗はより少なくなると考えています。例えば、
目標1 学校のテストで平均点(85点程度)を取る
目標2 中学受験も視野に入れて、レベルアップ
目標3 バリバリの中学受験をする!
それぞれに合わせた、問題集選びの具体について次の記事で書いていきます。
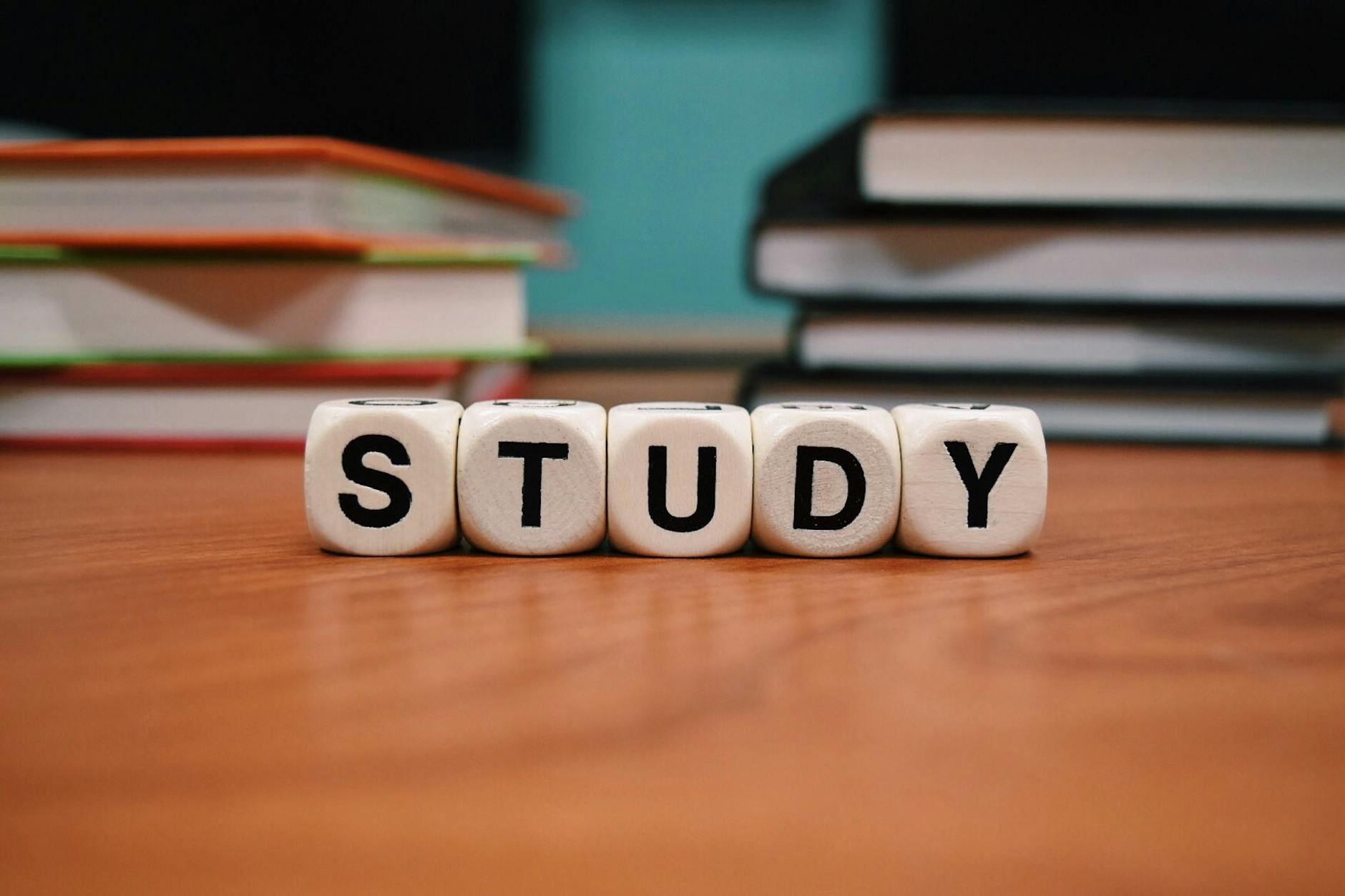
コメントを残す