目的や想定される「タイプ」を書いていますが、必ずしも一致する必要はなく、「このタイプが多い」という例で書いていますので、参考程度にご覧ください。
③ 信念(目的)を明確にして問題集を選ぶ
目的1:学校のテストで平均点(85点程度)を取る
タイプ:気分屋、ネガティブ、書いて覚える、学習習慣なし
復習向け
教科書と併用(確認用)
問題数や総ページ数は、少ないほど良い
問題集内の解き方の解説は不要
解答の解説が詳しい
計画表などは不要
授業後(テスト前)に取り組む問題集です。家庭学習として取り組むイメージです。教科書の問題と同程度で、「教科書の問題を一通り終わってから」取り組むのが理想です。
どうしてもわからないときには、解答の解説を見るようにします。問題を解く前に、解説が書いてある問題集もよくありますが、先に解法を見てから問題を解くと、自分の頭で考える習慣が身につきません。似た解き方を「当てはめ」て、答えを出してしまうのは、あまり良い習慣とは言えません。
問題集を解きながら、わからないことは基本的には教科書で確認します。※過去記事に書きましたが、日本の教科書より優れた「問題集」は特殊な目的(受験など)を除けば、ほぼありません。そのわかりやすさ、丁寧さは世界最高峰です。
問題数やページ数が少ない(=薄い)ということは、「重要なことだけが載っている」ということでもあります。さらに、「達成感を得やすい」というメリットもあります。周回(何度も解くこと)もできるので、分厚い問題集よりおススメです!
目的2:中学受験も視野に入れて、レベルアップ
タイプ:気分屋、ポジティブ、見て覚える、学習習慣なし
予習・復習、両方で使う
教科書と併用(確認用)
問題数や総ページ数は、少ない方が良い
問題集内の解き方の解説はあってもよい
解答の解説が詳しい
計画表などはあってもよい
目的1と比べると、「問題集『で』学ぶ」ことが増えます。教科書レベルでは「概念」を学んでいても、「解き方」の面で発展的な知識が必要になる場合があるからです。それでも、「概念」をなくして(教科書の内容をおろそかにして)、「解き方(処理)」のみを追求すると、学習が積み重ならなくなる危険性があることは、配慮する必要があります。
学習効率的に高いのは、圧倒的に復習です。予習は、学校の授業をより楽しむための学習と割り切った方がよいです。あるいは算数検定など、先取りの楽しさを感じられるものとセットで学ぶのが望ましいでしょう。
問題数や総ページ数もやはり少ない方がよいです。もっと多くの問題に取り組みたい場合は、類似の問題集をもう一冊用意するのがおすすめです。基礎レベルの問題が重なっても、問題ありません。必ず出る基礎問題を早く正確に解決できることは、テスト後半の難問に時間を割くために必須のスキルです。
発展問題も増えてくるので、問題個別の解説はあってもよいです。ただ、目的1の注意点は意識するのがよいと思います。
長期的な視点はあった方がよいです。例えば「学力コンクール」のような、規模の大きな模擬試験の試験範囲を確認して、そのためにどのペースで学ぶかを考えることは、主体的な学習者(アクティブ・ラーナー)となるためにも有効な学び方です。かといって、必須でもありません。子どもによっては、計画を立てることに夢中になりすぎて、かえって学習時間が減ってしまう…ということもあるので注意が必要です。
目的3:バリバリの中学受験をする!
タイプ:コツコツ型、ポジティブ、聞いて覚える、学習習慣あり
予習向け
問題数や総ページ数は少な目
問題集は複数冊
問題集内の解き方の解説が必須
解答の解説も詳しい
計画表などはないものが多いので自作
残念ながら、学校の授業と同ペースでは受験準備に間に合いませんので、予習がベースになります。つまり勉強効率は悪くなりがちです。
一冊当たりの問題数や総ページ数は少ない方がよいです。その分、分野ごとやジャンルで分けて取り組んだり、問題集の数は増やしてもよいです。ただ、分厚い本をひたすら解くのはメリットが少ないです。
問題も特殊なものが多くなりますので、解き方をしっかり理解するサポートが必要です。「なぜそうなるのか」を子供自身が納得できることが一番大切です。
このレベルの問題集は、計画表やご褒美シールなどはないことが多いです。しかし、本当はこのレベルの問題集を継続的に解く子供にこそ、評価システムが大切ですので、計画や評価を可視化する工夫が大切になります。
算数に絞ってになりますが、具体的におすすめの参考書は…
目的1
小学教科書ぴったりトレーニング(新興出版社)
小学 まとめノート 時間と単位の計算(増進堂・受験研究社)
目的2
【改訂版】小学校6年間の算数が1冊でしっかりわかる問題集 (かんき出版)
新傾向集中レッスン | 中学入試 算数 ルールの問題(文栄堂)
小学 まとめノート 時間と単位の計算(増進堂・受験研究社)
中学入試 でる順過去問 算数文章題 合格への368問(旺文社)
目的3
【改訂版】小学校6年間の算数が1冊でしっかりわかる問題集 (かんき出版)
中学入試 実力突破 | 算数 計算と一行問題 発展編(増進堂・受験研究社)
中学入試 算数図形問題完全マスター ハイレベル(数研出版)
新傾向集中レッスン | 中学入試 算数 ルールの問題(文栄堂)
中学入試 でる順過去問 算数文章題 合格への368問(旺文社)
などです、もちろん例示されていない問題集もお子様に合うものがたくさんあると思われます。例示された多くの問題集が塾にありますので、気になる方はお声がけくださいね!
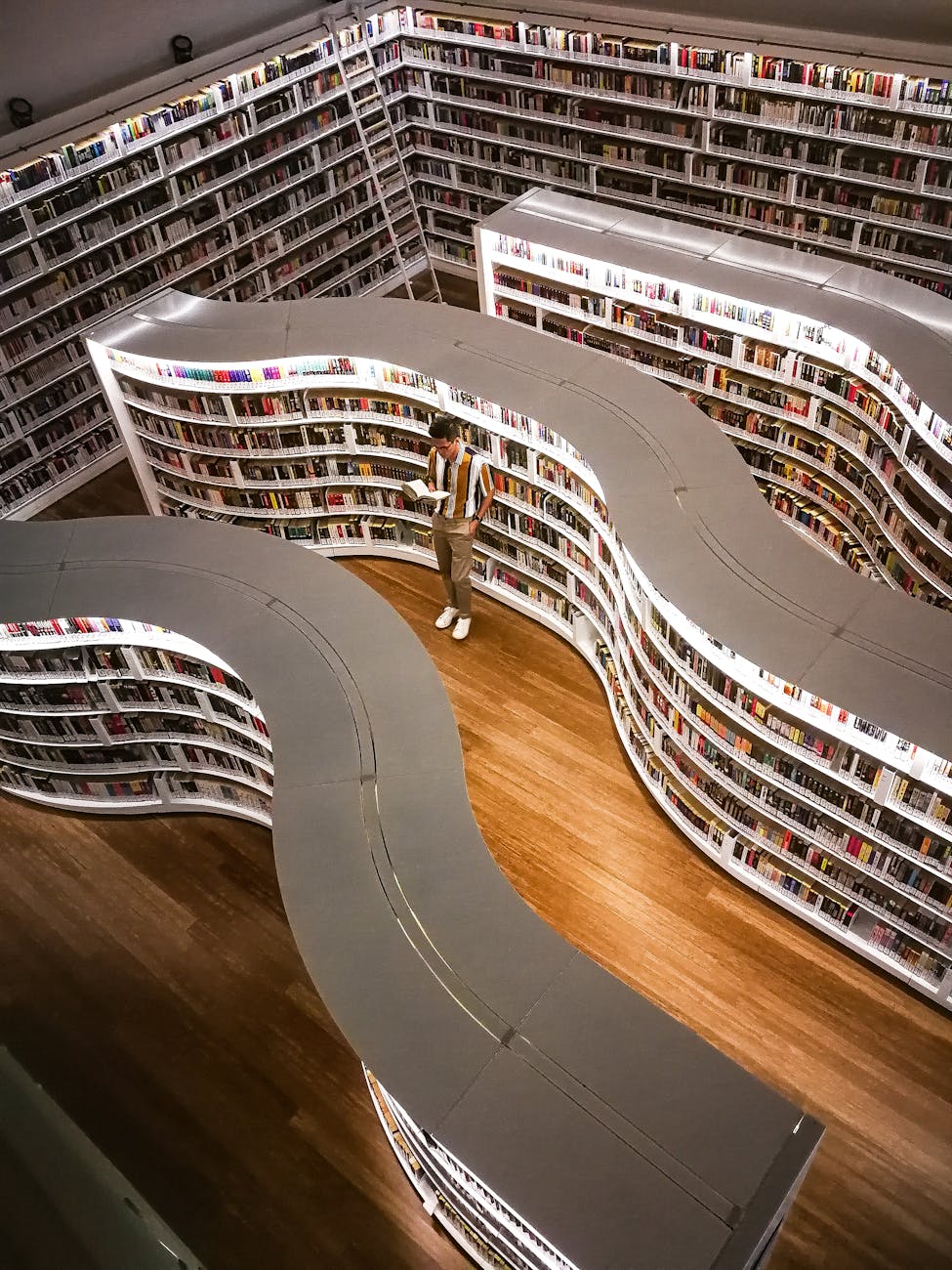
コメントを残す