子供がウソをつく理由のひとつに、「自分の思い通りにしたい」という気持ちがあります。たとえば、「先生がいいって言ったよ」「○○ちゃんが先にやったんだもん」など、事実を少し変えて伝えることで、自分の立場を有利にしようとする場面です。
これは、子供が人との関わり方やルールの中でどう振る舞えばいいかを試しているサインでもあります。社会の中で自分の居場所をつくろうとする、ある意味で前向きな行動とも言えるでしょう。
とはいえ、こうしたウソが繰り返されると、周囲との信頼関係に影響を与えることもあります。友達や先生との間に誤解が生まれたり、「あの子は信用できない」と思われてしまうことも。だからこそ、保護者が早い段階で気づき、やさしく対応することが大切です。
ウソを責めるのではなく、信頼を育てるチャンスとして捉えてみましょう。
たとえば、
- 「本当のことを話してくれてありがとう」
- 「ウソをつかなくても、ちゃんと気持ちは伝わるよ」
- 「どうしてそう言いたくなったのかな?」
といった声かけは、子供にとって「正直でいることの心地よさ」につながります。
また、ウソの背景にある気持ちに寄り添うことで、子供は「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じ、安心して本音を話せるようになります。これは、家庭の中で育まれる信頼の土台です。
ウソを通して、子供は少しずつ「誠実さ」「責任」「信頼」といった社会的な価値を学んでいきます。大人がそのプロセスに寄り添うことで、子供は安心して「正直な自分」でいられるようになります。
次回は、家庭で安心して話せるからこそ起こる“話の誇張”について。子供の話をどう受け止め、整理していくかを考えます。
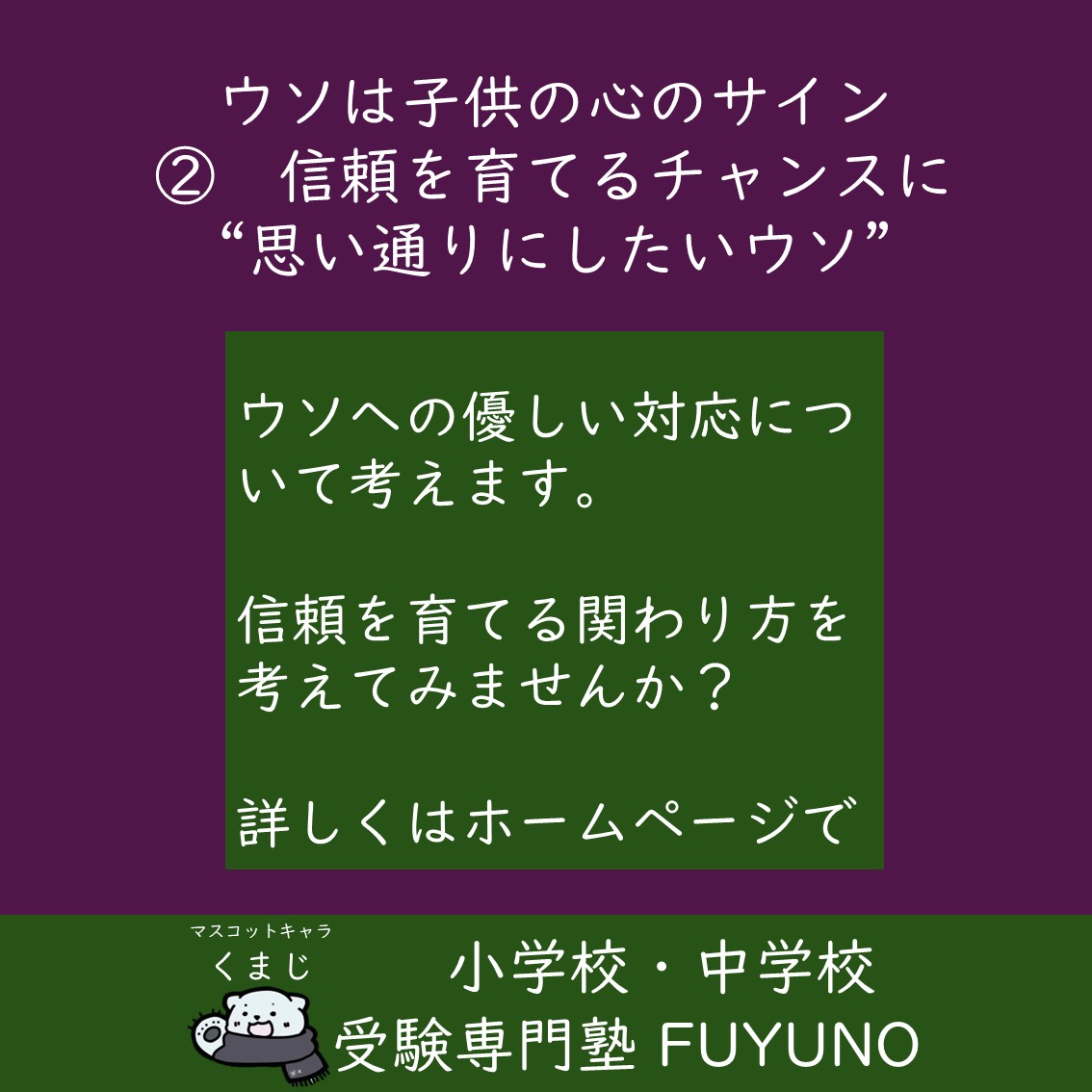
コメントを残す