家庭は、子供にとって安心できる場所です。だからこそ、学校での出来事を話すとき、子供は無意識のうちに話を誇張したり、事実を少し変えて伝えてしまうことがあります。
たとえば、「先生がすごく怒った!」という話も、実際には注意された程度だったり、「○○ちゃんがいじわるした!」という言葉の裏に、ちょっとしたすれ違いがあるだけだったりします。
これは、子供が自分の気持ちをわかってほしいという思いからくる自然な表現です。安心できる家庭だからこそ、感情がそのまま言葉になり、少し大げさになることもあるのです。
保護者として大切なのは、話の内容をすぐに「事実」として受け止めるのではなく、子供の気持ちと事実を分けて整理する力を育てることです。
「それはどんなふうに言われたの?」
「○○ちゃんは何て言ってた?」
「先生はどんな顔だった?」
こうした問いかけを通して、子供自身が出来事を振り返り、感情と事実を整理する習慣が育っていきます。
また、学校との連携も大切です。保護者が一方的に判断せず、先生と情報を共有することで、誤解やすれ違いを防ぎ、子供をより安心させることができます。
子供の話を丁寧に聞きながら、「正直に話しても大丈夫」「気持ちはちゃんと受け止めてもらえる」という安心感を育てること。それが、子供の社会性や信頼関係を築く力につながっていきます。
次回は、家庭と学校が協力することで、子供が安心して正直に生きる力を育む方法について考えます。信頼の橋渡しになる関わり方をお届けします。
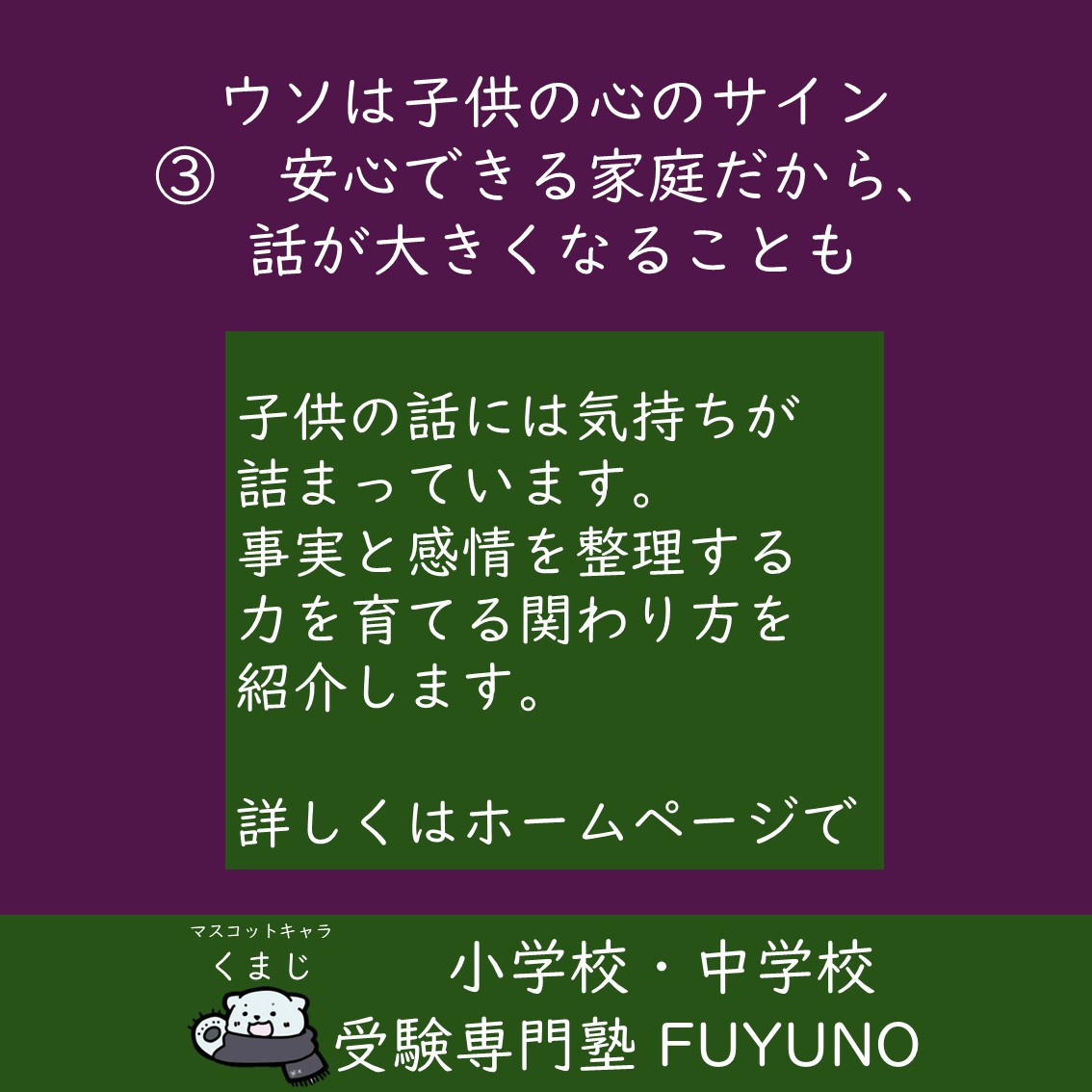
コメントを残す