最近では、生成AIを使って小学校受験の願書文を作成するご家庭が増えてきました。AIの進化によって、文章作成のハードルが下がり、誰でも手軽に整った文章を作れるようになったことが背景にあります。願書は、家庭の教育方針やお子さんの個性を伝える大切な書類ですので、「少しでも良いものを」と考える保護者にとって、AIは心強い味方になりつつあります。
AIの強みは、何といってもスピードと安定感です。キーワードやエピソードを入力するだけで、文法的に正しく、読みやすい文章を短時間で仕上げてくれます。語彙も豊富で、表現も多彩。自分では思いつかないような言い回しを提案してくれることもあります。
ただし、便利な一方で、いくつか注意すべき点もあります。まず、AIが作る文章は、どうしても「一般的」になりがちです。家庭ごとの価値観や、お子さんならではの個性が薄れてしまうことがあります。また、学校ごとの特色や求める人物像に合わせた調整が難しい場合もあります。願書は「誰に読まれるか」を意識して書く必要がありますが、AIはその読み手の気持ちまでは汲み取れません。
さらに最近では、受験塾などで指導される願書文も、ある意味で“型にはまった”内容になりがちです。塾側が過去の合格事例をもとにテンプレート化した文章を勧めることが多く、結果として、AIが生成する文章と似たような構成や表現になるケースも見受けられます。もちろん、塾の指導には一定の合理性がありますが、願書が「誰が書いても同じような内容」になってしまうと、学校側にとっては印象に残りにくくなってしまいます。
願書は、家庭の姿勢や子育てへの思いを伝える場です。整った文章であることも大切ですが、それ以上に「その家庭らしさ」が伝わることが重要です。AIや塾のテンプレートを活用する際には、必ずご自身の言葉で肉付けし、個性を加えることが求められます。
次回は、プロが作る願書文とAIの文章との違いについて、もう少し深く掘り下げてみたいと思います。
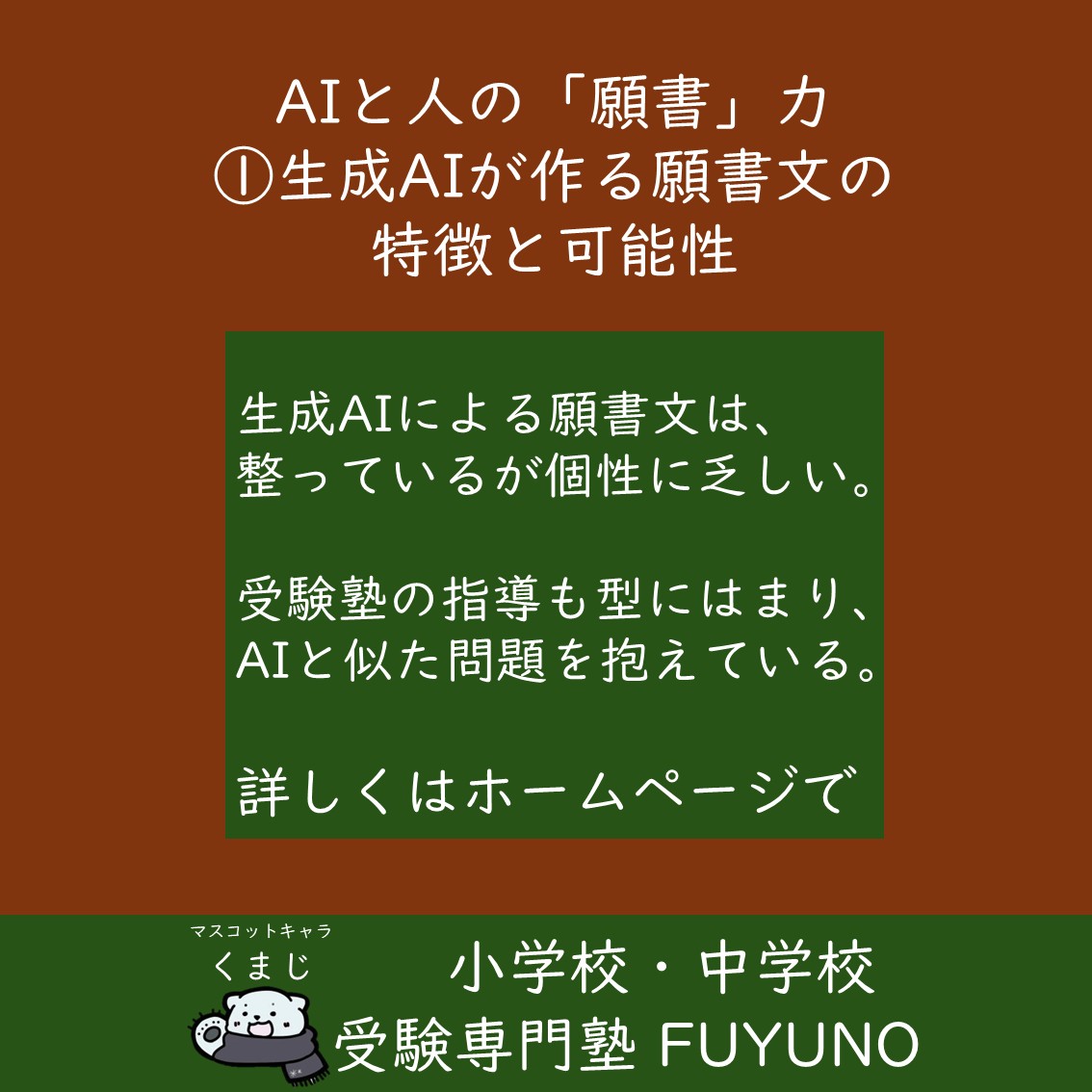
コメントを残す