最近では、生成AIを使って小学校受験の願書文を作成するご家庭が増えてきました。AIの進化によって、文章作成のハードルが下がり、誰でも手軽に整った文章を作れるようになったことが背景にあります。願書は、家庭の教育方針やお子さんの個性を伝える大切な書類ですので、「少しでも良いものを」と考える保護者にとって、AIは心強い味方になりつつあります。
AIの強みは、何といってもスピードと安定。前回は、生成AIによる願書文の特徴や可能性についてご紹介しました。今回は、実際にAIが作成した願書文を見ながら、その表現や構成、伝わり方について考えてみたいと思います。
以下は、ある私立小学校を想定して生成AIが作成した、志望動機とその経緯をまとめた願書文(約400字)です。
我が家では、子どもが自ら問いを立て、深く考える力を育むことを大切にしてきました。日々の生活の中で「なぜ?」を大事にし、親子で調べたり話し合ったりする時間を積み重ねてまいりました。そうした中で、貴校が探究的な学びを重視し、子ども自身の興味関心を尊重する教育方針を掲げていることを知り、大変共感いたしました。また、国際的な視野や多様性を大切にする姿勢にも強く惹かれました。説明会や学校見学を通じて、先生方の温かく丁寧な関わりや、子どもたちが主体的に学ぶ姿に触れ、ぜひこの環境で学ばせたいという思いが強まりました。貴校での学びを通じて、子どもが自分らしく成長し、社会に貢献できる力を育んでほしいと願っております。
一読して感じるのは、文章が非常に整っており、文法的な誤りや違和感がほとんどないという点です。語彙も豊かで、教育的なキーワードが自然に盛り込まれており、読みやすさという点では高い完成度を持っています。
一方で、読み手として気になるのは、「どの家庭にも当てはまりそうな内容」に見えてしまうことです。探究心や国際性といった言葉は魅力的ですが、具体的なエピソードや家庭の背景が見えにくく、印象に残りにくい印象を受けます。これは、AIが「家庭の空気感」や「保護者の声のトーン」を持たないことに起因しています。
また、実はこのような文章は、受験塾で指導される願書文とも非常に似ています。塾では合格実績のある表現や構成をもとに、ある種の“正解”を教える傾向があり、その結果、どの家庭の願書も似たような内容になってしまうことがあります。つまり、AIが作る願書文と、塾で指導された願書文が、意図せずして似通ってしまうという現象が起きているのです。
願書は、家庭の教育観やお子さんの個性を伝える大切な手紙です。整った文章であることも大切ですが、それ以上に「その家庭らしさ」が伝わることが重要です。次回は、プロが作成する願書文とAIの文章を比較しながら、「人が書く意味」について考えてみたいと思います。
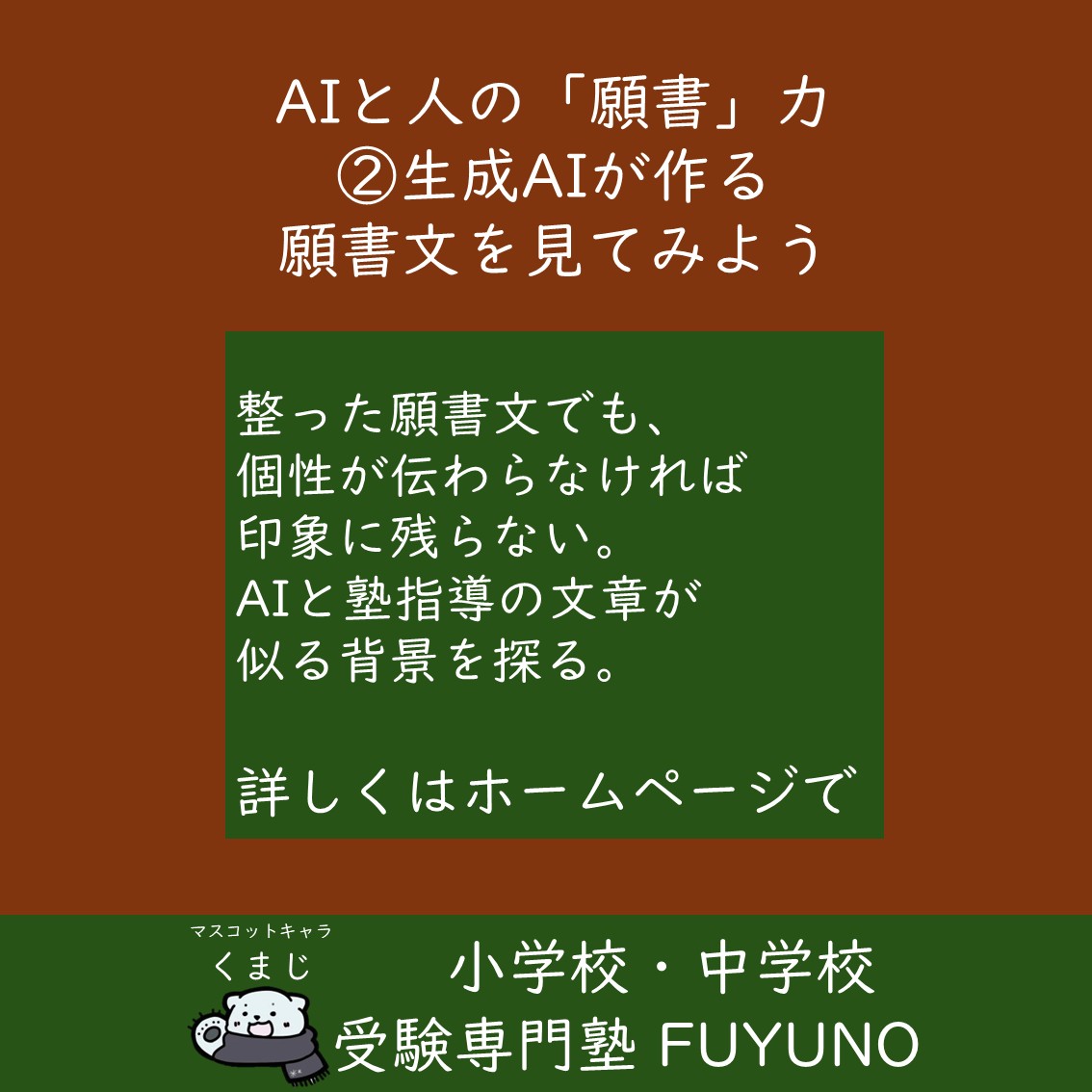
コメントを残す