第1回では生成AIによる願書文の特徴を、第2回ではその実例を紹介しました。今回は、FUYUNOが保護者とともに作成した願書文をもとに、「人が書くこと」の意味や、生成AIとの違いについて考えてみたいと思います。
以下は、FUYUNOのサポートを受けて作成された願書文の一例です。
志望動機(抜粋)
「学校見学に参加した際には、『英語の授業も図書館も楽しかった。あの学校に通ってみたい』と本人が語り、私どもも教育環境に強く魅力を感じました。主体性を育みながら、協調性や社会性を伸ばす教育方針は、我が家の子育ての軸と一致しており、ぜひこの環境で学ばせたいと考え、志望いたしました。」
子どもの特徴(抜粋)
「息子は好奇心が旺盛で、興味を持ったことには深く探究する姿勢があります。英語と絵が得意で、園ではクラフト作成時のお手本に選ばれることも多く、先生方からは積極的に関わる姿勢を評価いただいております。」
この文章は、生成AIが生成したものではなく、保護者の言葉をもとにFUYUNOが構成を整えたものです。文法や構成は整っていながら、何よりも印象的なのは「家庭の空気感」が伝わってくる点です。子どもの言葉や日常の様子が自然に盛り込まれており、読み手にとっては「その子らしさ」が感じられる内容になっています。なお今回は、特定を避けるために少しぼかした部分がありますので、実際の願書にはより具体的なエピソードが盛り込まれています。
プロが作る願書文は、さらに表現を磨き、構成を整える力がありますが、保護者自身が書いた文章には、プロには出せない「生活のにおい」や「親のまなざし」が宿っています。これは、読み手である学校側にとっても大きな意味を持ちます。
一方で、プロの文章は、学校ごとの傾向や評価ポイントを踏まえた戦略的な構成が可能です。願書文を「伝えるための手段」として最大限に活かすためには、プロの視点も有効です。ただし、そこに保護者自身の言葉が乗っていなければ、どこか空虚な印象になってしまうこともあります。
願書文は、家庭の想いや子どもの姿を学校に届ける「手紙」のようなものです。FUYUNOでは、保護者の言葉を丁寧に引き出し、学校の特色に合わせて言葉を整えるお手伝いをしています。AIやテンプレートでは伝えきれない「そのご家庭らしさ」を願書文に込めるために、ぜひご相談ください。
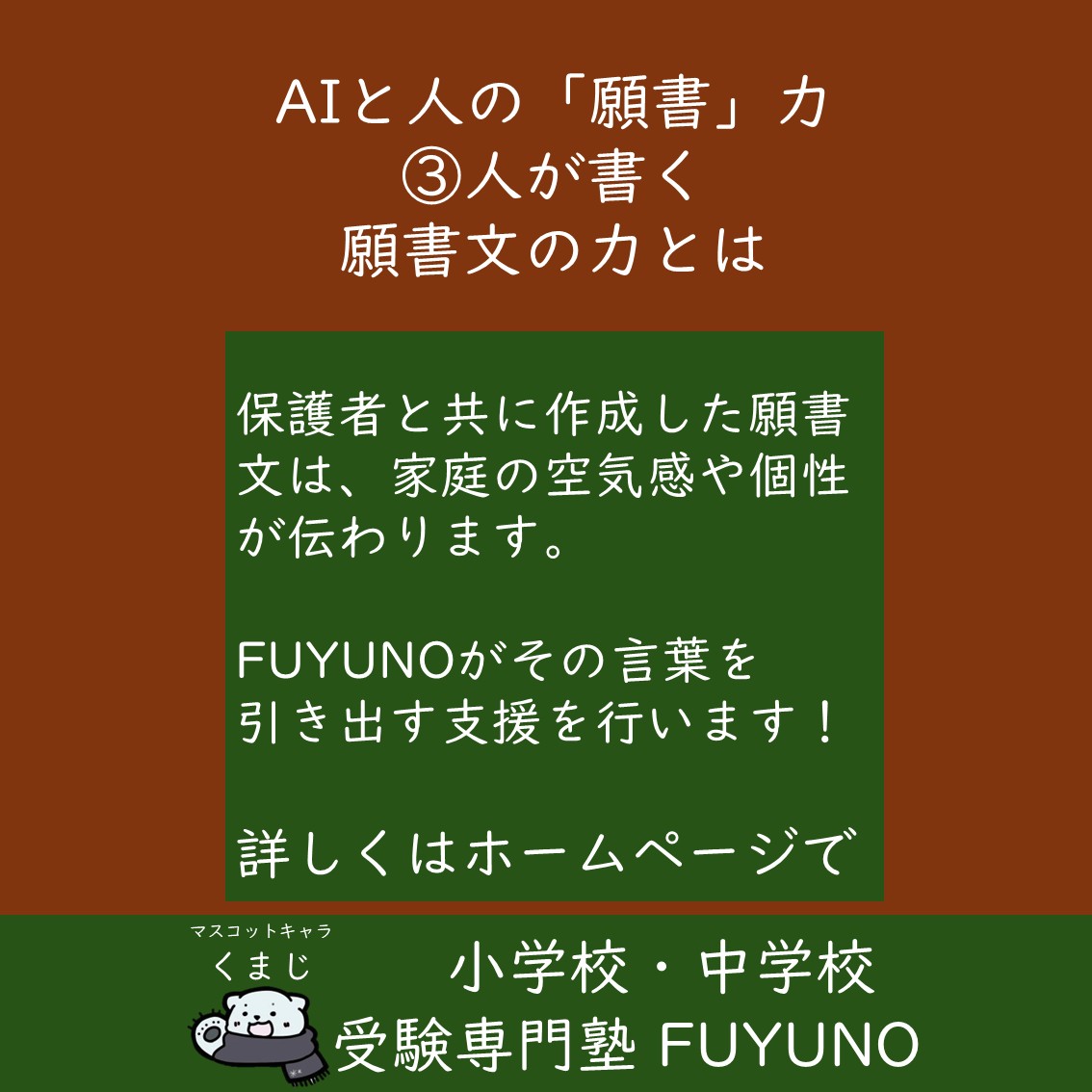
コメントを残す