「うちの子、算数が好きで先取りしてるんです!」
そんな声、最近よく聞きます。確かに、先に知っておくと安心だし、テストでも有利かも…と思いますよね。
でも、ちょっと待って。その“知ってる”が、考える力の芽を摘んでしまうこともあるんです。
「三角形の内角の和は180度」って、いつ学ぶの?
この内容は、小学5年生で学習します。
でも、ただの“知識”ではなく、「帰納法」という思考法を育てるための教材で出てくる内容なんです。「角度」の学習は4年生ですが、思考法(論理的思考)を学ぶには「1年待つ」判断をしているのが教科書(学習指導要領)です。
5年生の授業では、クラスのみんなが自由にいろいろな三角形を描いて、分度器で角度を測ります。
- 「この三角形は60度・70度・50度で…合計180度!」
- 「こっちは90度・45度・45度で…やっぱり180度!」
と、自分で測って、みんなと比べて、気づくという体験をします。
この「誰が描いても、どんな三角形でも、内角の和は180度になる!」という発見が、算数の醍醐味。
いろんな例から共通点を見つけて、法則に気付く――これが、「帰納法(きのうほう)」です。
帰納法とは、複数の具体的な事例から共通点を見つけて、一般的なルールを導く考え方です。
その気付きが、次の学びにつながる
この発見をもとに、今度は「じゃあ四角形はどうなる?」と考えます。
ここで登場するのが、「演繹法(えんえきほう)」です。
例えば、四角形に補助線を引いて三角形を2つ作ると…
- 「三角形が2つだから、180度 × 2 = 360度になる!」
と、すでにわかっている三角形の性質を使って、論理的に新しいことを導く力が育ちます。
演繹法とは、すでにわかっているルールを使って、別の事柄を論理的に導く考え方です。
でも、先に“答え”を知ってしまうと…
もし4年生の段階で「三角形の内角の和は180度だよ」と“答え”だけ教えてしまったら?
子どもは「なんでそうなるの?」を考える機会を失ってしまいます。
そして、5年生の授業が「ただの確認作業」になってしまうことも…。それを避けるためには、知識を分断するのではなく、丸ごと系統性を保持したまま、学ぶことが大切になります(例:カリキュラム(教育課程)レベルで構成し直して、5年生単元をまるごと4年生で取り組むなど)。
保護者の皆さんへ
先取り学習は、うまく使えば力になります。
でも、「知識」だけを先に与えると、「考える力」を育てるチャンスを奪ってしまうことも。大人が知っていることも、「どうしてそうなるのかな」「本当にそうかな」という声掛けを大切にしていきたいものです。
算数は、答えを出すことよりも、どう考えるかが大切。
ぜひ、お子さんが「気付く喜び」を味わえるよう、見守ってあげてくださいね。
先生方へも、ひとこと
この「三角形の内角の和は180度」という内容、つい先に教えたくなる気持ち、よくわかります。
でも、もし子どもが「それ知ってる!」と言ってきたら、
「本当にそうなの?どうしてそうなると思う?」と、問い返してみてください。
その一言が、子どもたちの思考の扉を開くきっかけになります。
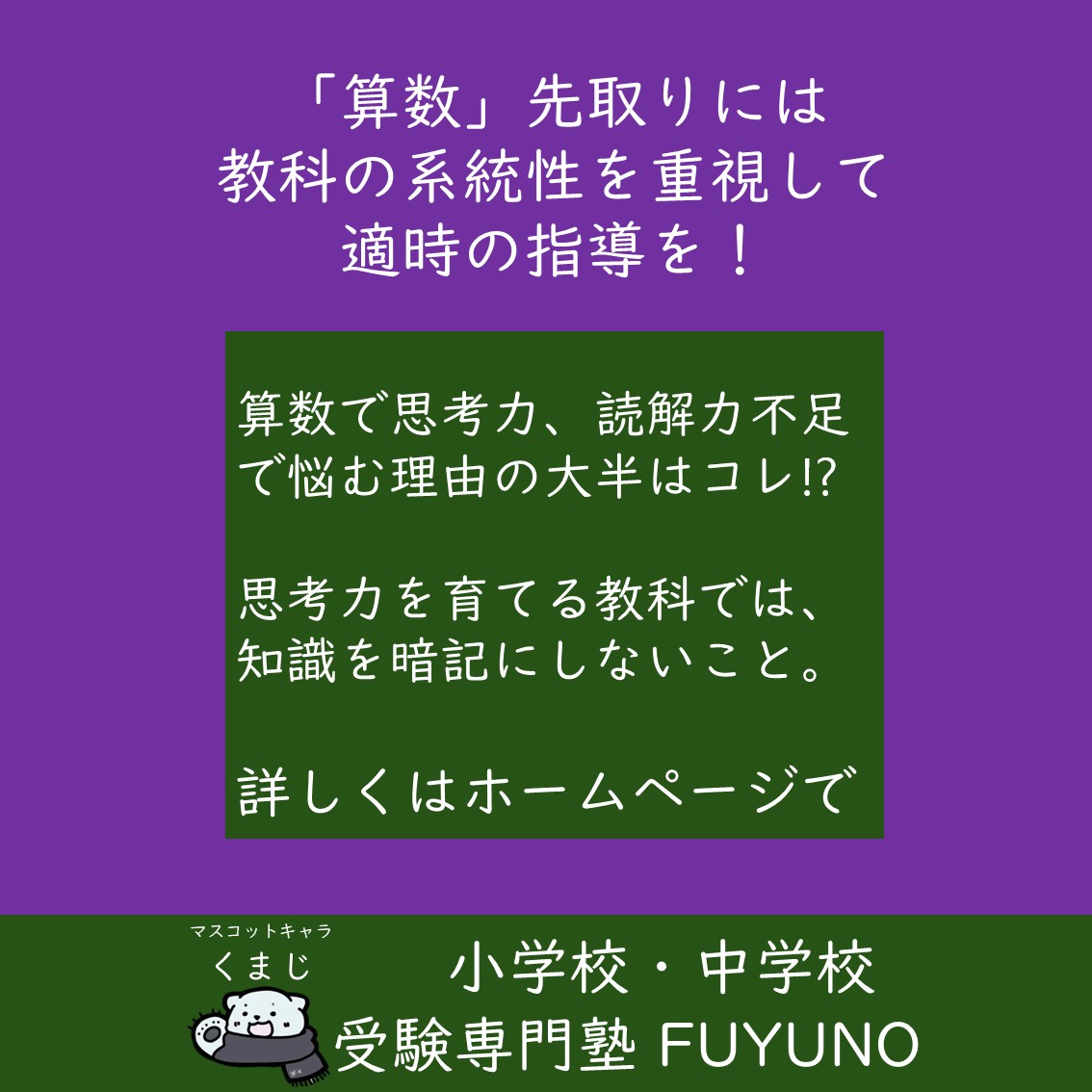
コメントを残す