「“あわせて”って言ってるからたし算でしょ?」
「“ちがい”って言ってるからひき算だよね?」
低学年の算数でよく見られる、こんな“インスタントな答えの出し方”。
実はこれ、考える力を育てるチャンスを逃してしまうことがあるんです。
算数は「言葉」だけで解けるものじゃない
算数の文章題には、場面のイメージがとても大切です。
でも、「“あわせて”って書いてあるからたし算」とだけ覚えてしまうと、場面を想像する力が育ちません。
例えばこんな問題:
りんごが3こ、みかんが2こあります。あわせてなんこでしょう?
この場合、「あわせて」という言葉からたし算を選ぶのは自然です。
でも、もし問題がこうだったら?
みかんはりんごより2こすくないです。みかんは5こあります。りんごはなんこでしょう?
多くの子供が「少ない」につられてひき算をします。もちろんこれはたし算で処理すべき問題。
実は、中学受験を控えた5年生、6年生でも間違う子供が結構います。「読解力がない」「ケアレスミスが多い」という悩みを抱えていた要因は、低学年時に上のような学び方をしてきたことであり、「低学年の時はよくできていた」子が、考え方がわからず上の学年になって苦労する、というのは「算数あるある」です。
つまり、言葉だけで判断するのではなく、場面をイメージして考えることが大切なのです。
単位に〇をつけて、答えにもそのままつける?
これもよくある学習のクセです。
「5こ」「2こ」と書いてあるから、答えにも「〇こ」とつける。
でも、単位は意味を考えてつけるものです。
例えば:
みかんが5こあります。りんごはみかんより2こ少ないです。りんごは何こでしょう?
この場合、答えは「3こ」。
ただその答えを出す過程が、「『少ない』だからひき算で、単位は〇をつけた『こ』だから、5-2=2で3こ」と書いていたら、算数に大切な「場面を考えて式を立てること」を育てるチャンスを失ってしまっています。
これは、場面を考えずに“型”だけで答えてしまう典型例。
算数の本質から離れてしまう危険があります。
「言葉に反応してすぐに計算する」クセは、早く答えを出すことにはつながります。
でも、算数の本質は考えること。
場面をイメージし、何を求めているのかを理解する力が、これからの学びに大きく影響します。
ぜひ、お子さんが問題を読んだときに、
- 「どんな場面かな?」
- 「何がわかっていて、何を求めているのかな?」
と考える時間をもてるように、声かけしてみてください。
また、「問題作り」をさせるのも有効です。場面を想像して、自分なりの言葉で、式の意味を創造することは、算数的な学びにはとても大切な取り組みと言えます。
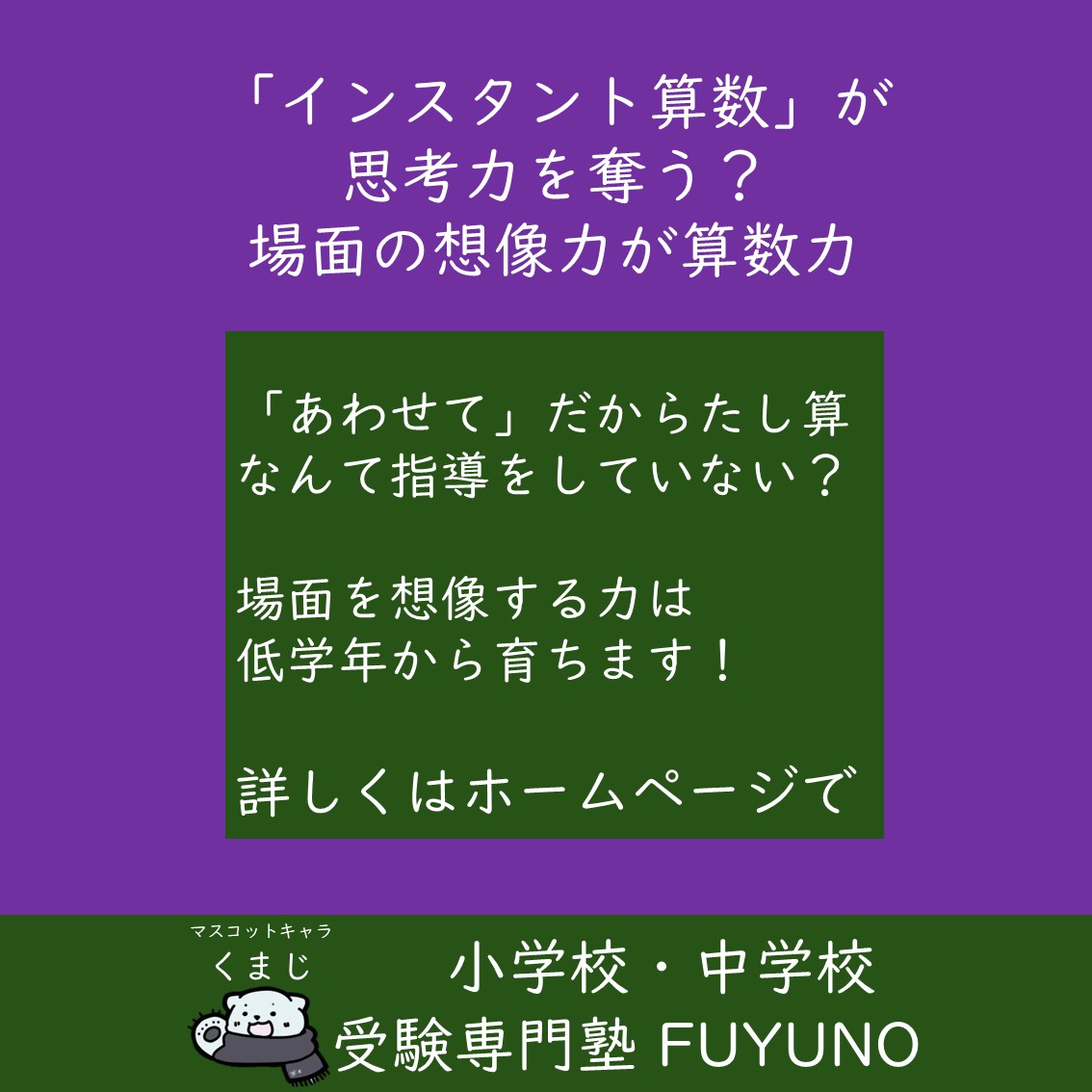
コメントを残す