〜評価の仕組みと先生の葛藤〜
「テストの点数がそのまま成績になるなんて、ちょっと極端じゃない?」
そう感じたことがある保護者の方もいるかもしれません。でも、今の学校現場では、それが“やむをえない選択”になっている背景があります。
近年、学校には「成績の根拠を示す責任」が強く求められるようになってきました。
保護者や教育委員会から「この評価の理由は?」と問われたとき、先生が「授業中の様子を見て…」と答えるだけでは納得されないこともあります。そこで、テストの点数が“客観的な証拠”として重視されるようになったのです。
とはいえ、先生方は決して点数だけで評価しているわけではありません。
授業中の発言、提出物、取り組みの様子など、日々の学びを丁寧に見取り、記録しています。中には、毎時間の評価をメモに残し、通知表の成績に反映させる工夫をしている先生もいます。こうした“見えにくい評価”を可視化する努力は、子供の学びを多面的に捉えるために欠かせないものです。
しかし、その労力は非常に大きく、先生方の負担感や労働時間にも影響しています。
本来は「子供の学びを支える」ことが中心であるべき教育活動が、いつの間にか「成績をつけるための仕事」に時間を奪われてしまっている――そんな現場の声も少なくありません。
さらに、業者テストや標準化された問題は、全国的な比較ができる一方で、学校の授業内容や子供の生活経験とずれていることもあります。
たとえば、問題文に出てくる言葉が子供にとって馴染みのないものであれば、算数の力とは関係なく点数が下がってしまうこともあります。これは、テストが本来測るべき力をうまく捉えられていない、ということでもあります。
こうした制度的な背景や評価の仕組みを知ることで、保護者としても「点数だけで子供の力を判断するのは危うい」という視点を持つことができます。
テストの“正しさ”は、制度や仕組みの中で揺れ動くもの。だからこそ、結果を受け止めるときには、少し距離を置いて考える余裕が必要なのかもしれません。
次回は、「テストの結果をどう活かすか」に焦点を当てます。
点数を見て終わりにせず、そこから何を学び、どう支えるか。
家庭でできる工夫について、一緒に考えてみましょう。
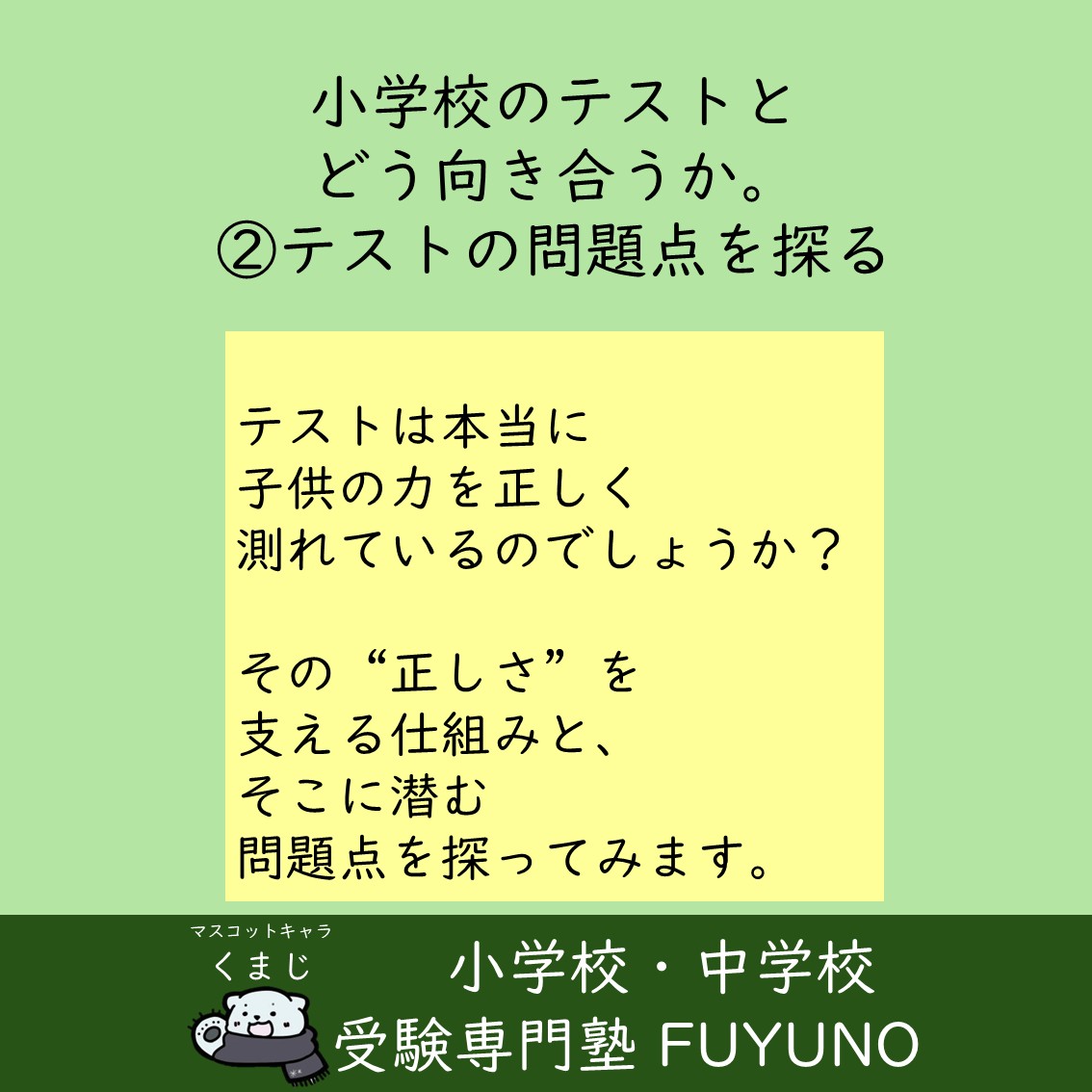
コメントを残す