〜「見えない理由」に目を向ける〜
テストの点数が思わしくないと、「うちの子、ちゃんと理解できていないのかも…」と不安になることがあります。特に低学年では、保護者の反応が子供の自己評価に直結しやすく、学びへの意欲にも影響を与えかねません。
でも、低学年のテスト結果には、実はさまざまな“見えない理由”が隠れていることがあります。
例えば算数の問題で、文字が読めなかった、言葉の意味が分からなかった、知らない物が出てきた――そんな理由で答えられなかったこともあるのです。理解していないわけではなく、問題文のハードルに引っかかってしまっただけかもしれません。
仮に、先生がそうした背景を読み取ったうえで、60点だった子に「算数的な力には問題ない」と通知表で◎をつけたとしましょう。逆に、70点だった子に「実力通りの点数」として○をつけたら、保護者から「なぜうちの子の方が低評価なのか」と疑問が出るかもしれません。点数と評価が一致しないことで、学校側が説明責任を問われるリスクもあるのです。
テストの結果と通知表の成績の関連は、教務主任・教頭先生がチェックしていますので、このような場合、担任の先生は「この成績の根拠は説明できる?」と聞かれます。担任の先生はそれぞれなので、「根拠はあるけど、保護者に伝えられるか不安」「管理職に注意された」などと感じ、こう聞かれるケースを避ける先生もいると考えるの自然でしょう。管理職の中にも、「説明しなくてはいけない状況は極力避けたい」と考える人もいるかもしれません。
そんな理由で、今の学校現場では「テストの点数=通知表の成績」という構図が強まっています。先生の裁量で評価することが難しくなり、結果として、テストの点数だけが子供の学びを示す指標になってしまうのです。
さらに低学年では、集中力や気分、直前のトラブルなど、テストに臨む環境そのものが結果に大きく影響します。大人が考える以上に、子供のテスト結果には多くの要因が絡んでいるのです。
だからこそ、通知表の成績も含めて、おおらかにとらえる視点が大切です。点数に振り回されるのではなく、「この結果から何を学べるか」「どう支えていくか」を考えることが、子供の学びを支える第一歩になります。
次回は、「テストの問題点」に向き合います。
点数がすべてではないと分かっていても、やっぱり気になる“その根拠”。テストの信頼性や妥当性、そして学校側の事情について、少し深く考えてみましょう。
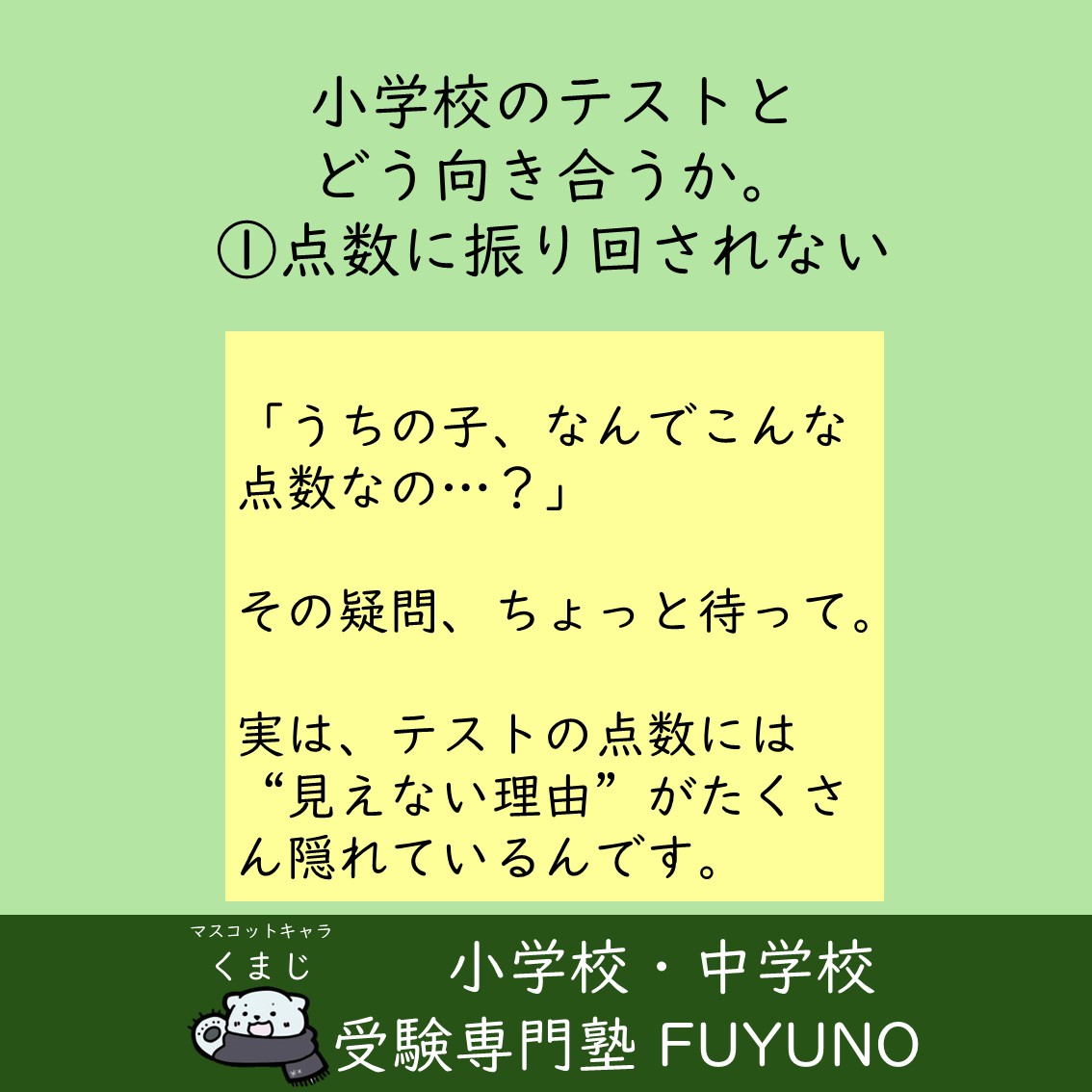
コメントを残す