国語は、国語の授業だけで使うもの――そう思われがちですが、実は学校生活のあらゆる場面で必要とされています。
たとえば、理科や社会の授業。問題文を読んで、何を問われているかを理解する力は、まさに読解力です。図や表の説明を読み取る力も、国語の力が土台になっています。
算数でも、文章題になると「何を計算すればいいのか」がわからなくなる子がいます。これは、計算力ではなく、読解力の問題です。つまり、国語力が他教科の理解にも深く関わっているのです。
でも、国語の力が活きるのは、教科の中だけではありません。今の学習指導要領では「協働的な学び」が重視されており、話し合いやグループ活動が増えています。自分の考えを伝え、相手の話を聞き、共通点や違いを見つけていく――こうした活動には、言葉の力が欠かせません。
表現力は、単に「うまく話す」ことではなく、相手の立場や気持ちを想像しながら伝える力です。つまり、他者理解の力でもあります。子供たちが「どう言えば伝わるかな?」と考えることは、相手を思いやる第一歩なのです。
国語は、単なる「教科」ではなく、学びと人との関係をつなぐ力です。子供たちが学校で出会うさまざまな課題に向き合うとき、国語の力がそっと背中を押してくれます。
保護者の皆さんが、子供の「話す」「書く」「読む」力に目を向けてくださることは、学び全体を支える大きな力になります。国語は、すべての教科と、そして人との関係とつながっている――そのことを、ぜひ心に留めていただけたら嬉しいです。
🔜次回予告(第2話)
次回は、国語力が高いとどんな表現ができるようになるのかを見ていきます。語彙力や構成力が育つことで、子供の考えがより深く、魅力的に伝わるようになります。
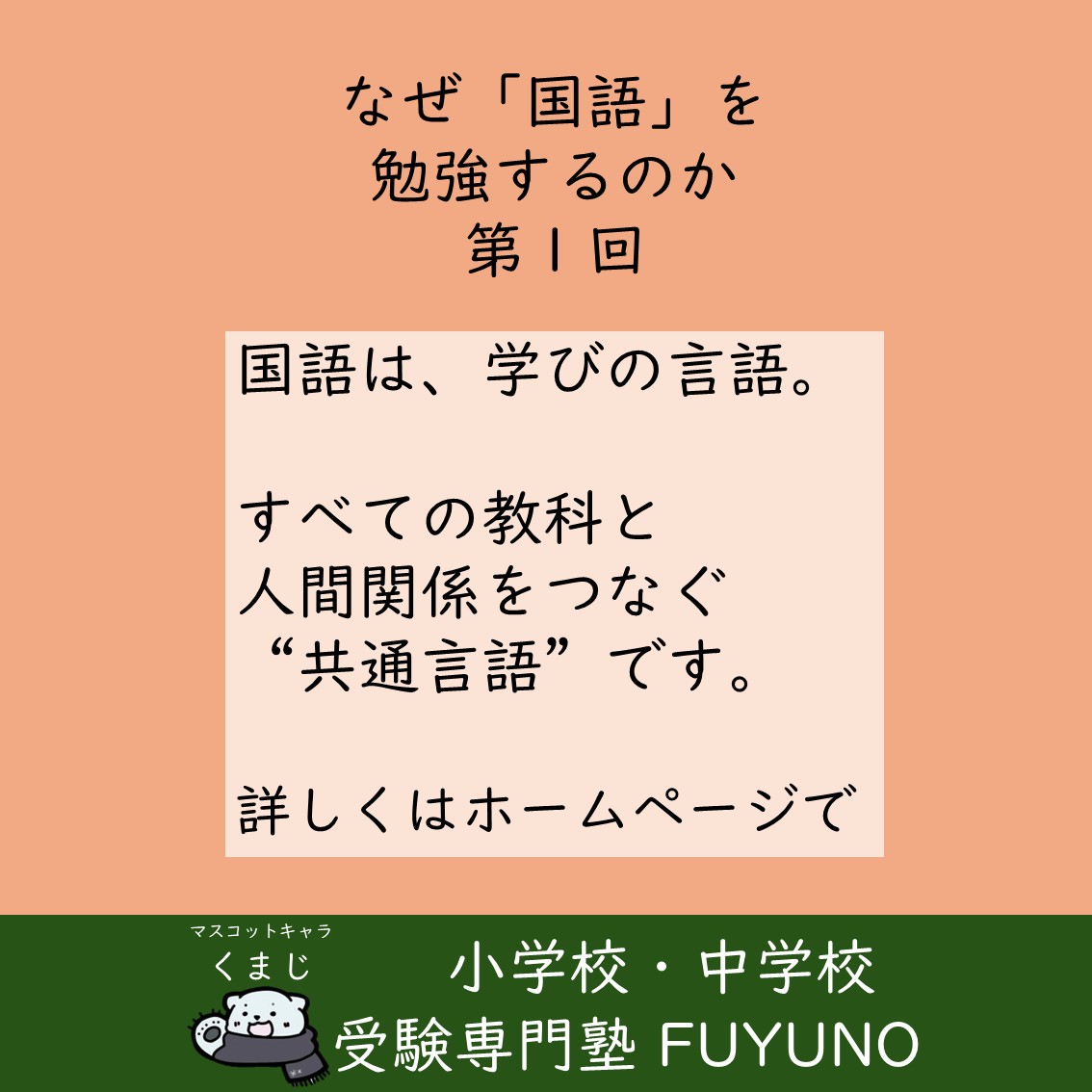
コメントを残す