「この子、ちゃんと考えてるのに、うまく言えないんです」
そんな声を、保護者の方からよく聞きます。実は、考える力と伝える力は別物。どんなに深く考えていても、それを言葉にできなければ、相手には伝わりません。
国語力が高い子は、語彙が豊かで、構成力があります。つまり、「何を」「どんな順番で」「どんな言葉で」伝えるかを選ぶ力があるのです。これは、単なるテストの得点以上に、他者との関係を築く力になります。
たとえば、「楽しかった」だけで終わらず、「○○があって、びっくりしたけど、最後は笑っちゃった」と言える子は、聞き手の想像力を引き出します。こうした表現は、相手の理解を助け、共感を生みます。
今の教育では、「協働的な学び」が重視されています。話し合い活動やグループワークでは、自分の考えを伝えるだけでなく、相手の意見を受け止め、言葉を交わしながら理解を深めていきます。ここで必要なのが、伝える力=表現力です。
表現力は、単なる技術ではなく、他者理解のための言語的な橋渡しです。言葉を通して、自分の考えを届けると同時に、相手の考えにも耳を傾ける。その繰り返しが、子供の世界を広げていきます。
国語は、子供の「伝えたい」を「伝わる」に変える教科です。その力が育つことで、子供たちは自分の考えに自信を持ち、他者との関係を築く力を身につけていきます。
🔜次回予告(第3話)
次回は、「言葉は体験から育つ」という視点から、日常の中で子供の言葉がどう育まれていくかを見ていきます。親子の会話や体験が、国語力の土台になります。
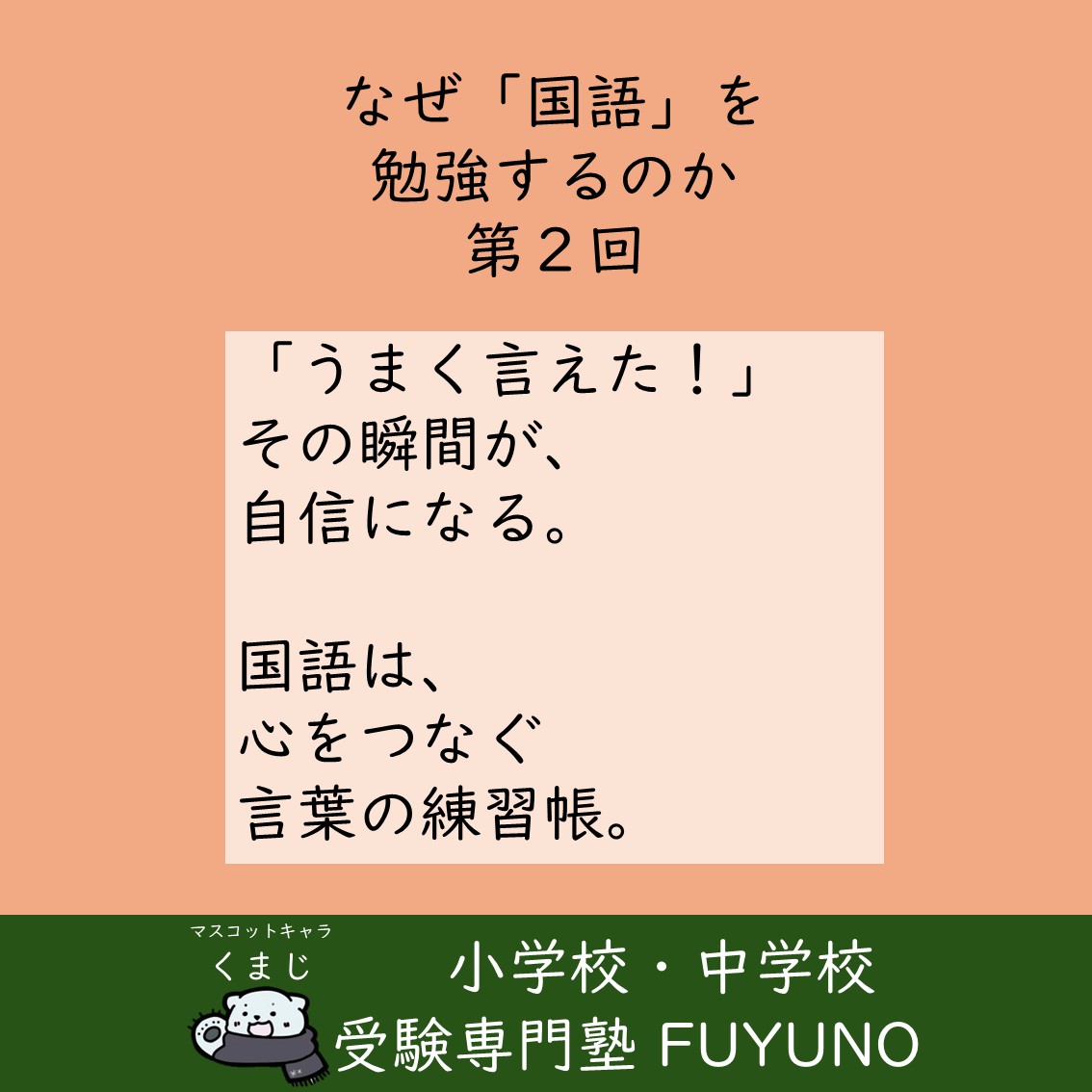
コメントを残す