「プログラミング的思考」は、塾や学校だけで育つものではありません。むしろ、日常生活の中にこそ、その芽はたくさんあります。今回は、家庭でできる関わり方についてご紹介します。
まず大切なのは、「順序立てて考える」場面を意識して作ること。たとえば、料理の手順やお出かけの準備など、生活の中には自然な流れがあります。「何から始める?」「次は何をする?」と声をかけるだけで、子どもは自分の頭で順番を考えるようになります。
次に、「条件によって行動が変わる」場面を活用すること。「雨が降ったら傘を持つ」「晴れなら帽子をかぶる」といった選択は、まさに条件分岐の考え方です。親が先回りして準備するのではなく、「今日はどうする?」と問いかけることで、子ども自身が判断する力を育てることができます。
また、失敗を責めず、「まずはやってみる」ことを応援する姿勢も大切です。うまくいかなかったときに、「どうすればよかったと思う?」と振り返る時間を持つことで、試行錯誤する力が育ちます。これは、プログラミング的思考の根っこにある「改善していく力」です。
FUYUNO塾でも、アリロやシンク・シンクなどの教材を使って、失敗から立ち直る経験を大切にしています。家庭でも、ブロック遊びや迷路、簡単な工作などを通して、「考えて試す→うまくいかない→考え直す」という流れを作ることができます。
最後に、親が「察して動く」のではなく、「言葉で伝えさせる」こともポイントです。「お母さん、紙!」ではなく、「プリントを書くから紙がほしい」と言えるようになることが、思考の整理につながります。これは、国語力にも直結する力です。
家庭でのちょっとした声かけや関わり方が、子どもの思考力を大きく育てます。プログラミング的思考は、未来を生きるための力。塾と家庭が連携して育てていけたら、子どもたちはもっと自由に、もっと柔軟に考えられるようになるはずです。
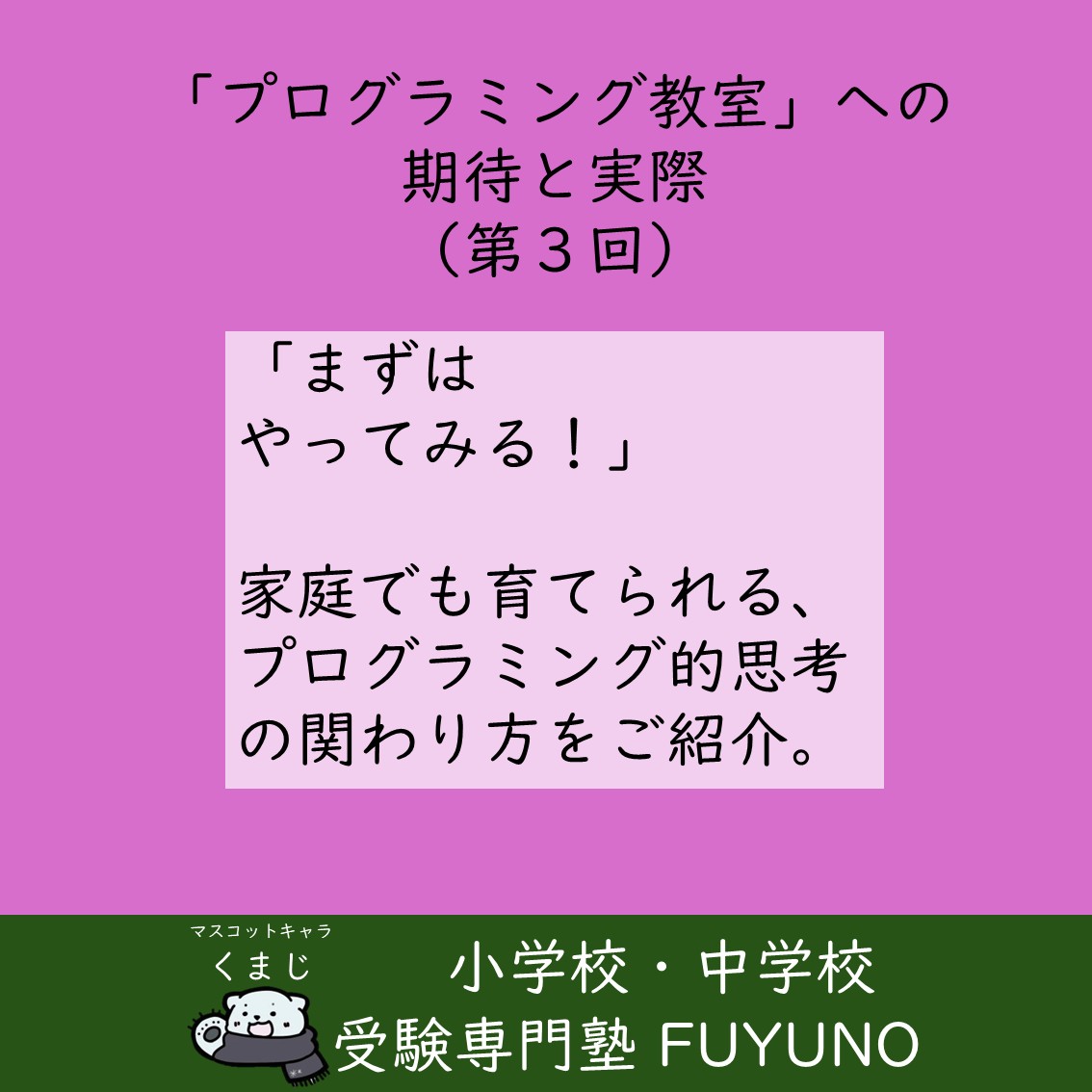
コメントを残す