「速さ」は、日常でもよく使う言葉です。時速60km、秒速5mなど、耳にする機会は多く、子供たちにとってもなじみのある言葉でしょう。ところが、5年生の算数で「速さ」を学ぶと、急に難しく感じる子が増えます。なぜでしょうか?
その理由の一つは、「速さ」という量が、「2つの異なる量(距離と時間)を組み合わせた“単位量あたりの大きさ”」であることにあります。たとえば「時速60km」は、「1時間で60km進む」という意味です。これは、今までの「長さ」や「時間」といった、直感的に理解できる量とは異なり、抽象的な“割合”の感覚が必要になります。
この「単位量あたりの大きさ」を理解するために、教科書では事前に「1あたり量」の学習が行われます。しかし、ここでつまずく子も多いのです。なぜなら、「1あたり量」は割り算の考え方と深く関係しており、割り算の意味があいまいなままでは理解が進まないからです。
さらにさかのぼると、割り算の前提には「かけ算」の理解があります。かけ算は本来、「1あたり量 × いくつ分」という構造で成り立っており、この「1あたり量」は、2年生の頃に「○○ずつ」という言葉で学んでいます。つまり、「○○ずつ」は「割合」の感覚とつながっているのです。
ところが、5年生で学ぶときには、「○○ずつ」と「単位量あたりの大きさ」が別物のように扱われてしまうことがあります。これが、子供たちの混乱を招く原因の一つです。
このシリーズでは、「速さ」の学習がなぜ難しいのかを、学年をまたいで丁寧にひもときながら、本質的な理解を育てるための視点をお伝えしていきます。
次回予告:
次回は、「単位量あたりの大きさ」と「○○ずつ」の表現が、なぜ子供たちにとってつながりにくいのかを掘り下げます。
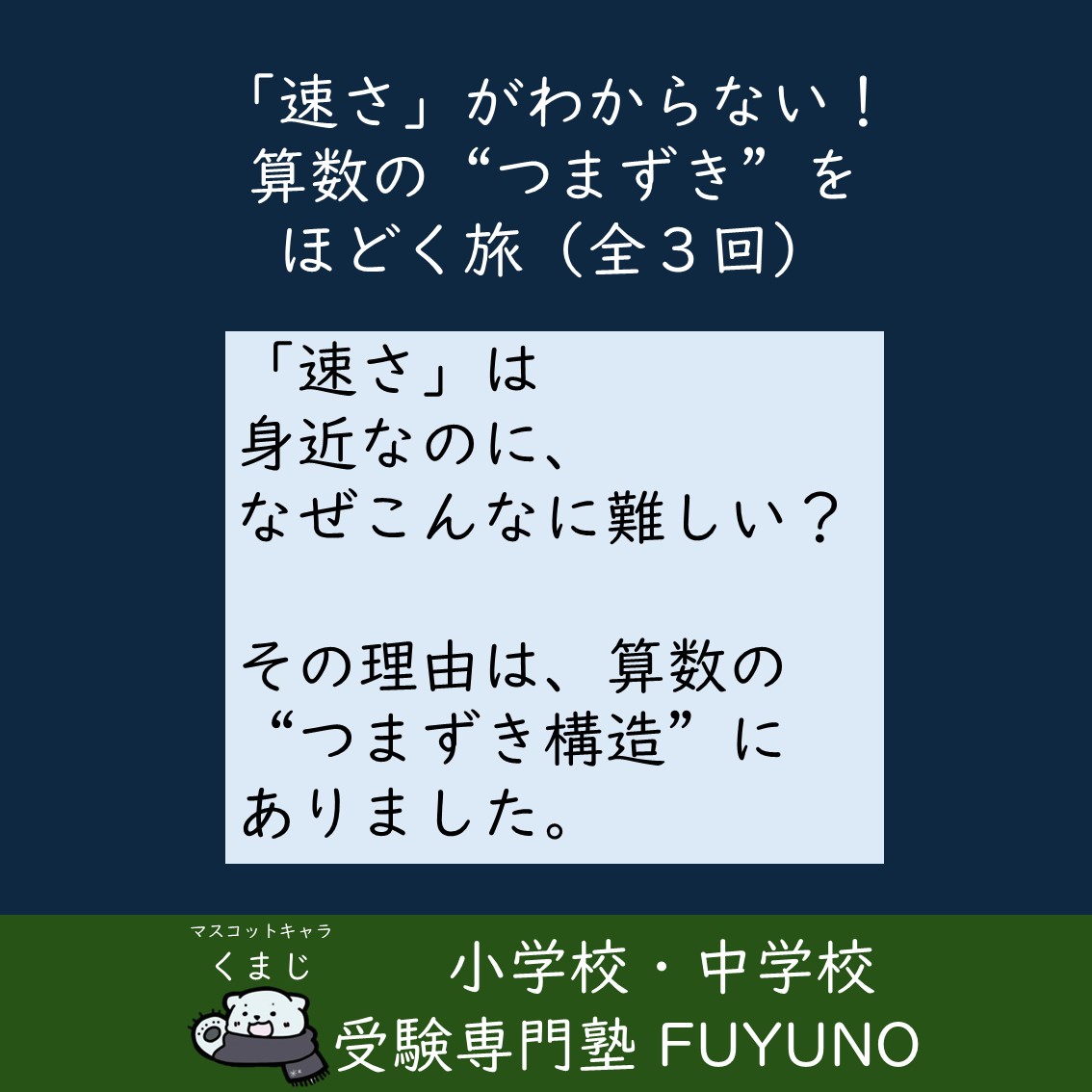
コメントを残す