「速さ」の学習で、子供たちが混乱する理由の一つが、「かけ算で解くのか?割り算で解くのか?」という問いです。速さの公式は「速さ=距離÷時間」ですが、問題によっては「距離=速さ×時間」や「時間=距離÷速さ」となるため、どれを使えばいいのか迷ってしまうのです。
この混乱の背景には、かけ算と割り算の意味の理解が不十分なまま公式に頼ってしまうという構造があります。たとえば、「1秒で5m進むとき、20秒で何m進むか?」という問題は、「○○ずつ × いくつ分」という2年生のかけ算の構造で考えられます。これは自然に理解できます。
しかし、「60m進むのに3秒かかった。速さは?」という問題になると、「距離÷時間」という割り算の公式を使うことになります。さらに、「割り算は大きい数から小さい数を割るもの」という誤ったイメージをもっていると、意味がつかめなくなります。
本来、割り算は「全体をいくつかに分ける」または「1あたりの量を求める」ためのものです。つまり、「60mを3秒で進んだ」という状況は、「1秒あたり何m進んだか」を求める問題であり、1あたり量の考え方が必要なのです。
このように、「速さ」の問題は、かけ算と割り算の両方の意味を正しく理解していないと、公式だけでは「適用」はできても、「応用」することができません。公式は便利ですが、意味を伴わない公式の暗記は、思考力の育成を妨げることにもなります。
「速さ」は、単なる計算ではなく、「どんな関係があるのか」を考える力を育てる絶好の題材です。かけ算と割り算の意味を行き来しながら、関係性を理解することが、算数の本質的な学びにつながります。
次回予告:
次回は、「はじきの図」で終わらせない、思考力を育てる速さの学びについて考えます。
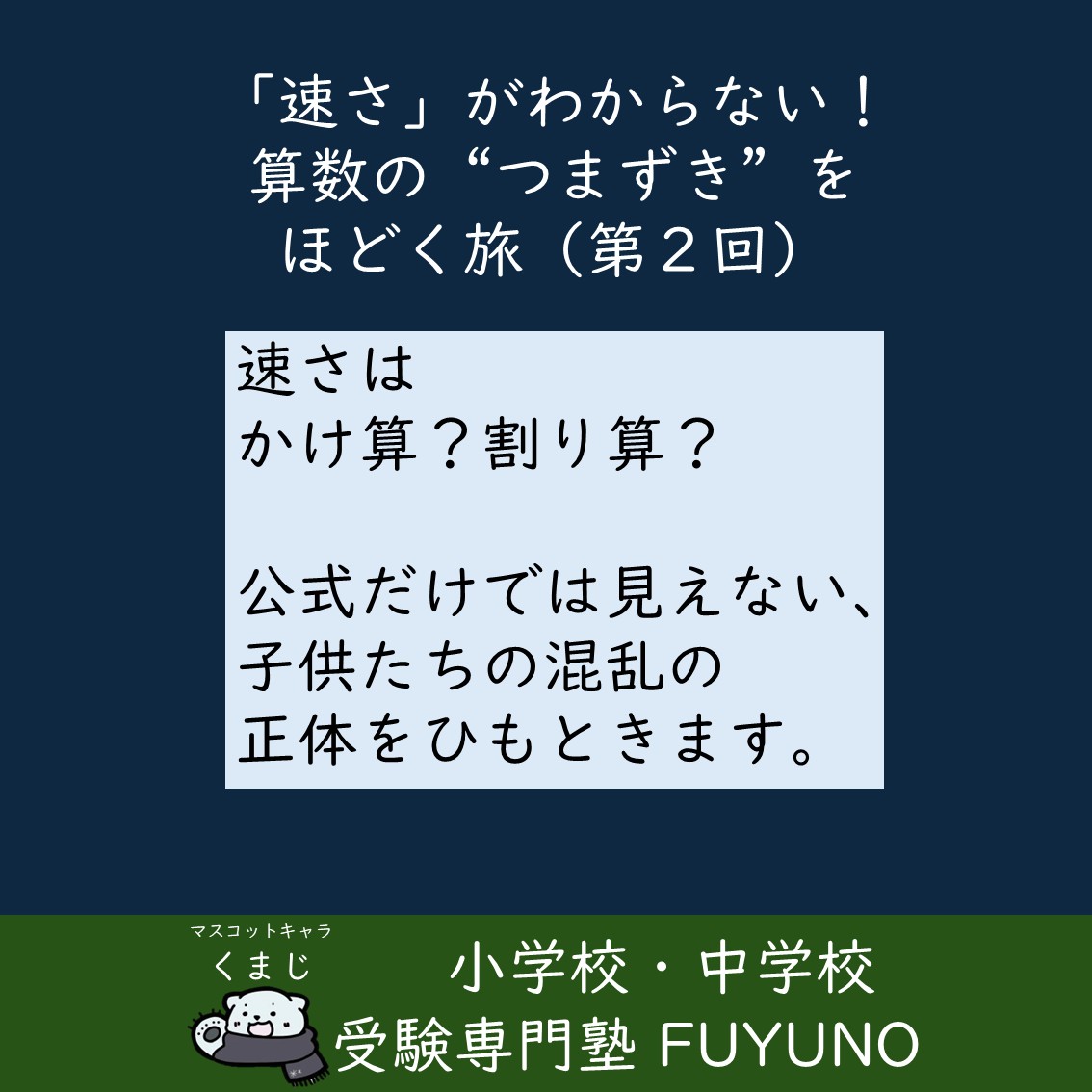
コメントを残す