「速さ」の学習でよく使われるのが、「はじき(みはじ)の図」です。速さ・時間・距離の関係を三角形に当てはめて、どの公式を使えばいいかを視覚的に整理するものです。確かに便利な道具ですが、これだけで学習を終えてしまうと、算数の本質である“関係を考える力”が育ちません。
「はじきの図」は、公式を選ぶための補助にすぎません。本来、速さの学習は「どんな関係があるのか」「どの量が変化すると、他の量はどうなるのか」といった比例の考え方を育てる絶好の機会です。
たとえば、「1秒で5m進むなら、20秒で何m進む?」という問題は、「○○ずつ × いくつ分」というかけ算の構造で考えられます。これは、時間が2倍になれば距離も2倍になるという比例関係を自然に理解することにつながります。
一方、「60m進むのに3秒かかった。速さは?」という問題では、「1秒あたり何m進むか」という1あたり量の考え方が必要です。このように、速さの学習には、かけ算・割り算・比例・単位量といった複数の概念が絡み合っています。
それなのに、「はじきの図」で公式を選んで、数字を当てはめて終わりにしてしまうと、関係性を考える力が育たず、文章題になると手が止まるという事態を招きます。これは、目先の計算ができることを重視しすぎた結果です。
もちろん、計算ができることは大切です。しかし、それだけでは「速さ」を理解したとは言えません。速さとは、関係を読み解く力を育てる教材なのです。その本質に触れることで、算数が「できる」から「わかる」へと変わっていきます。
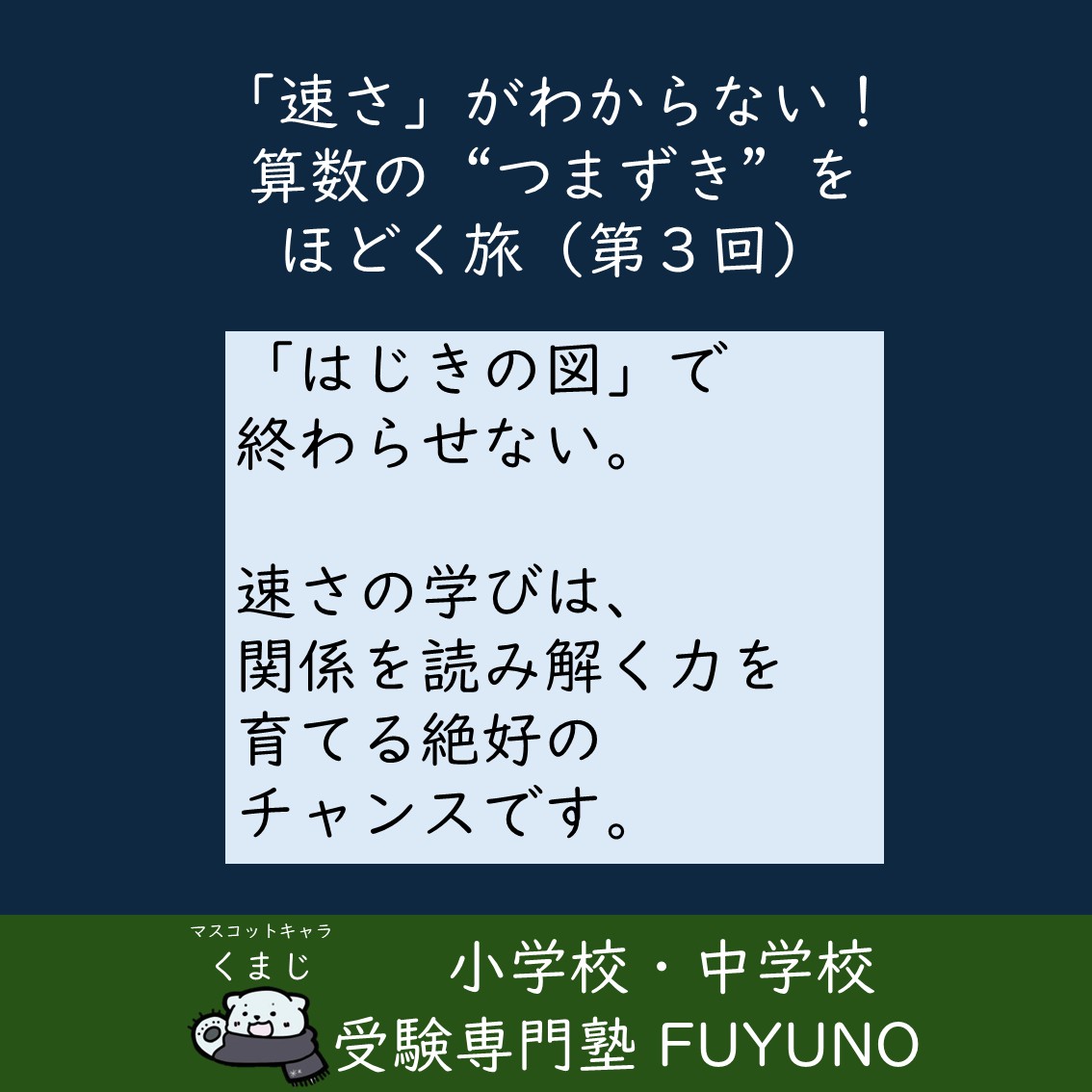
コメントを残す