「うちの子には、こんな環境で育ってほしい」
そう思って小学校受験を考える保護者の方は、少なくありません。実際に学校見学などで目にする今の小学校の教室は、昔とはずいぶん様子が違います。子どもたちは自由に意見を交わし、時にはぶつかり合いながらも、互いを認め合って学び合っています。先生が一方的に話すのではなく、子どもたちが授業を動かしているような、そんなアクティブな雰囲気。見ているだけで、ワクワクするような空間です。
そんな学級の様子を見て、「うちの子にもこんな環境を」と思うのは自然なことです。特に、得意なことに夢中になれるタイプの子どもにとっては、自由な発言や活動が許される場は、まさに理想の学びの場に見えるでしょう。親としても、子どもの才能を伸ばすために、より良い環境を探したくなる気持ちはよくわかります。
けれど、ここで一つ立ち止まって考えたいことがあります。
その理想の学級は、どうやって成り立っているのでしょうか。自由に見えるその空間は、実は「自由にしていいよ」と言われているわけではありません。子どもたちが自分の行動をコントロールできるからこそ、先生は安心して任せることができる。つまり、自由の裏には「自律」があるのです。
この「自律」が、実は小学校受験で最も問われる力のひとつです。
静かに待つことができる。指示をもれなく聞ける。友達と協力して行動できる。元気に「はい」「わかりました」「ありがとうございます」と言える。こうした力は、自由な学びの場を支える「ブレーキ」のようなもの。アクセルだけでは、理想の教室は走り出せません。
次回は、この「ブレーキ」がなぜ受験で重視されるのか、そしてその背景にある教育観について、もう少し深く掘り下げてみたいと思います。
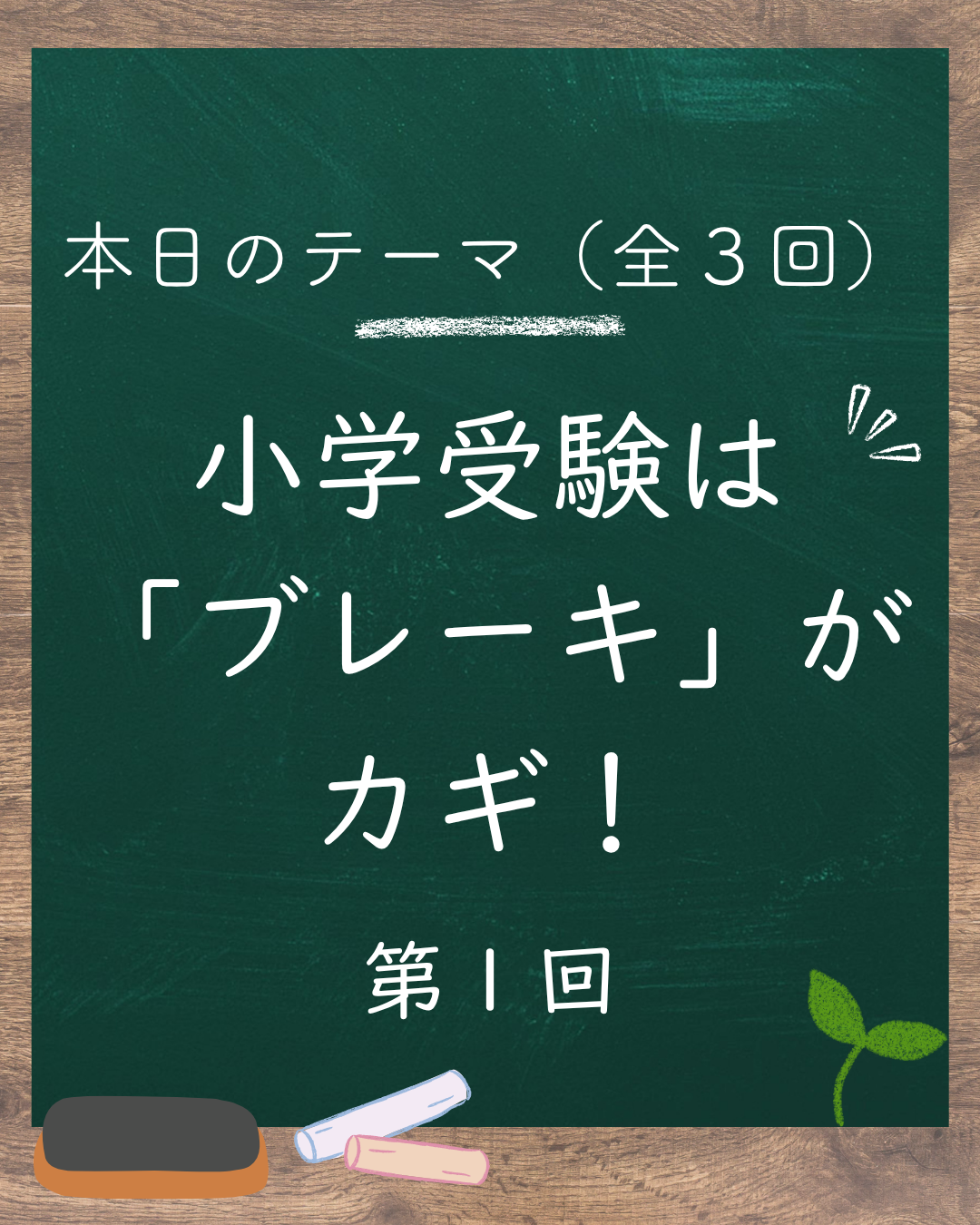
コメントを残す