「自由な学びの場で育てたい」と願って小学校受験を決めたのに、実際の試験では真逆の力が求められる。そんな矛盾に戸惑う保護者の方は少なくありません。
試験で見られるのは、静かに待てるか、指示をもれなく聞けるか、友達と仲良く行動できるか。元気に「はい」「わかりました」「ありがとうございます」と言えるかどうか。つまり、子どもが自律的に行動できるかどうかが問われるのです。
この「自律」は、自由な学びの場を成立させるための前提条件です。
自由に見える教室も、実は「自由にしていいよ」と言われているわけではありません。先生が安心して子どもたちに任せられるのは、子どもたちが自分の行動をコントロールできるから。アクセルだけではなく、しっかりとした「ブレーキ」があるからこそ、教室は安全に進んでいけるのです。
先生は、子どもたちの推進力を信じて授業を進めます。でも、もし方向がずれたときには、先生が手綱を握って修正する。その保証があるからこそ、自由な学びが可能になる。つまり、自由な環境は「自律」があってこそ成り立つものなのです。
受験で求められる「昭和スタイル」は、単なる昔ながらの教育ではありません。むしろ、現代の自由な教育を支える土台としての「自律」を見ているのです。だからこそ、試験では「静かに待つ」「指示を聞く」「協調する」といった力が重視されるのです。
次回は、才能のある子どもにとって最適な環境とは何か、そして学校という集団の中で育つ力について考えていきます。
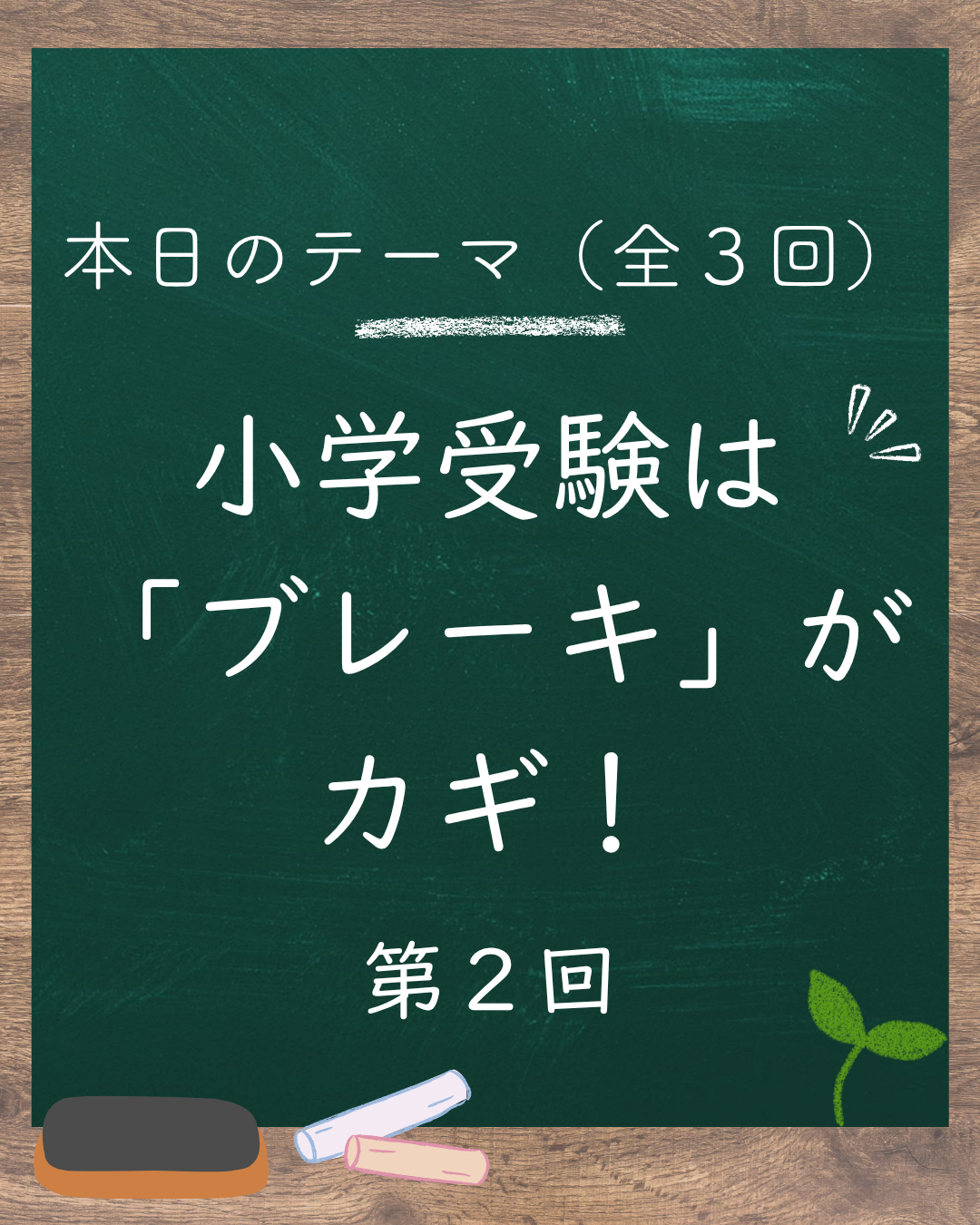
コメントを残す