願書文は、子どものことを書くもの。そう思われがちですが、実はその文には、家庭の空気や価値観がにじみ出ています。
たとえば、「いつも元気に登校しています」と書かれていれば、「元気であること」を大切にしている家庭なのだと読み取れます。「人の話をよく聞きます」とあれば、「聞く姿勢」を重視していることが伝わります。こうした言葉の選び方には、日々の会話や関わり方が自然と反映されているのです。
願書文は、うまく書こうとすると、かえって“らしさ”が消えてしまうことがあります。誰かに言われたような言葉や、よくある表現ばかりが並ぶと、「この家庭らしさ」が見えづらくなってしまうのです。
大切なのは、その家庭ならではの言葉で書くこと。
「朝の支度を自分でできるようになったことが、家族の中で小さな誇りになっています」
「妹に絵本を読んであげる姿に、私たちが教えた優しさが育っていると感じます」
そんな一文には、家庭の時間や思いがにじみ出ています。
願書文は、家庭の“言葉の風景”を映す鏡のようなもの。
だからこそ、日常の中でどんな言葉を交わしているかが、願書文の土台になります。
次回は、「願書文の“もったいない表現”」について考えてみましょう。
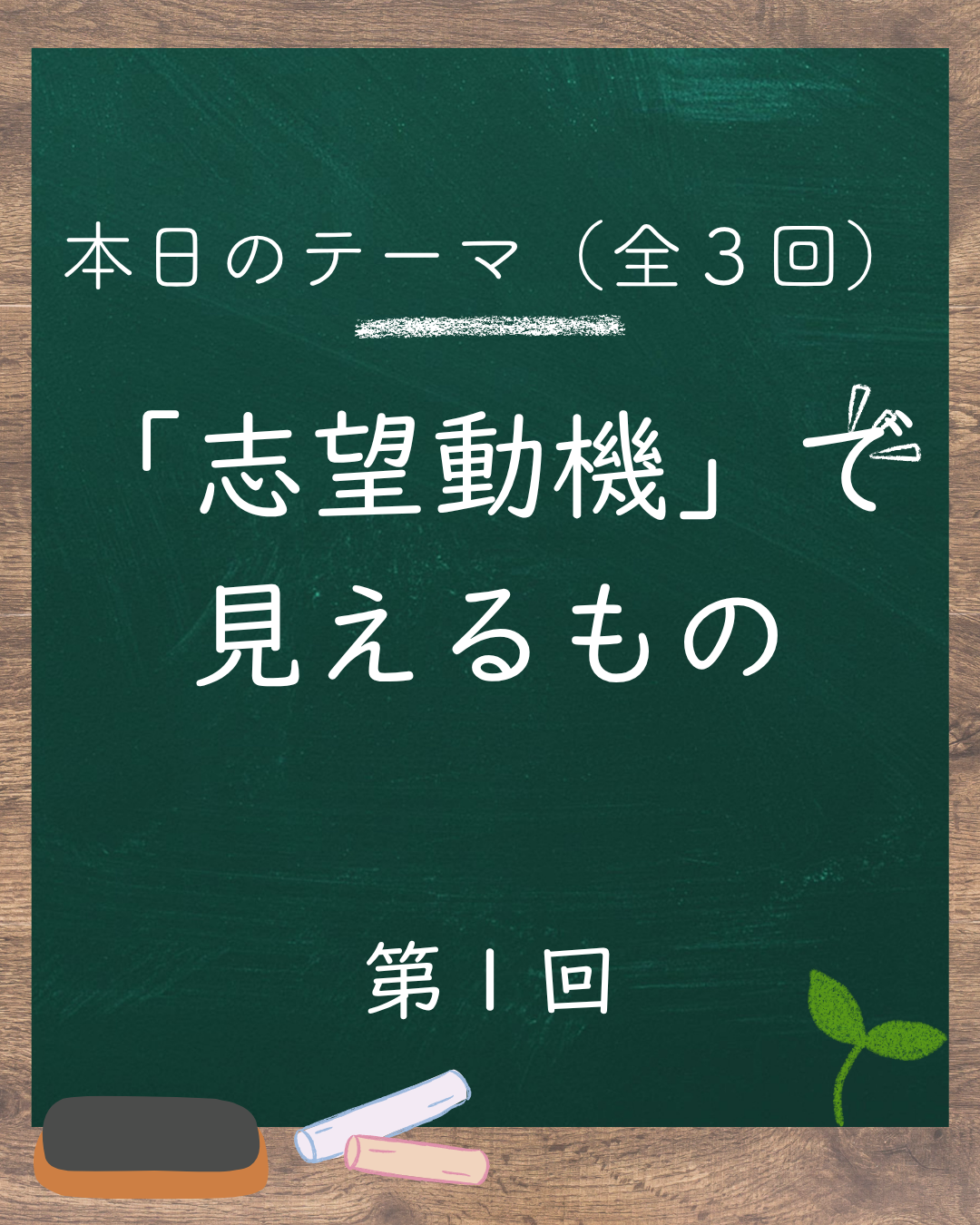
コメントを残す