「AIを使うと、読む力や書く力、考える力が育たないのでは?」
そんな声を耳にすることがあります。確かに、AIが文章を“代わりに”書いてくれるように見えると、「自分で考えなくなるのでは」と心配になるのも無理はありません。
でも、実際に使ってみると、AIを活用するにはむしろ「読む力」「書く力」「考える力」が必要だということがよくわかります。
たとえば、自己推薦書を書くとき。AIに文章を提案してもらうには、まず自分の経験や思いを言葉にして伝える必要があります。そして、出てきた文章を読んで、「これは自分の気持ちに合っているか?」「もっとこういう表現にしたい」と判断する力が求められます。
実際、わが子がAIを使って推薦書の草案を書いてもらったとき、「自分が伝えたいことを、文法的に正しい言い回しだとどう表されるのか」を実体験として学ぶ場面が何度もありました。
絵の指導を例に考えてみましょう。絵が苦手な子に対して、「感性が大事」「思いのままに描きなさい」とだけ言う指導——これは一見自由を尊重しているようで、実はとても不親切です。基本的な描き方や構図の“型”を知らなければ、自由に描くことはできません。文章も同じです。表現の型を知ることで、初めて自由な表現が可能になるのです。
AIは、その“型”を学ぶための優れた教材になります。よい文とそうでない文を見分ける力、伝えたいことを整理する力、そしてそれを言葉にする力——これらは、AIを使っても使わなくても、結局必要になる力です。
これからの時代に必要なのは、「情報に適切に関わり、使いこなす力」。AIも含め、デジタルのサポートを受けながら、自分の考えをより深く、より広く伝える力が求められていくでしょう。
「履歴書は手書きで」「年賀状は絶対手書き」「計算はそろばんが確実」——こうした価値観が今も残っているように、「文章は自分の力だけで書くべき」という考え方も、少しずつ変わっていくのかもしれません。
もちろん、手書きや自力で書くことにも意味があります。でも、それだけが「正しい」わけではなく、AIを活用することもまた、子どもたちの力を引き出す一つの方法です。
親としては、「AIを使う=ズル」ではなく、「AIを使って、自分の力を育てる」という視点で見守ることが大切なのではないでしょうか。
最後にAIで作成した自己推薦書を載せておきます。どのように感じますか?また、AIで書いたことを見抜けるでしょうか。そして最後に、この文章を書くために必要なスキルについて考えていただけると幸いです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私は、人と関わることが好きで、日本とちがう文化や考え方にふれることに強い関心があります。小学校の行事で、外国から来た学生さんと交流することがありました。はじめは英語でうまく話せるか不安でしたが、ジェスチャーや簡単な言葉を使いながら気持ちを伝えるうちに、言葉のかべをこえて心が通じる楽しさを知りました。この経験を通して、英語を学ぶことの大切さを実感し、文化のちがいを理解し合うことの大切さにも気付きました。
それから、英語の勉強に力を入れるようになり、外国の文化や生活についても自分で調べるようになりました。本を読んだり、インターネットで調べたりする中で、世界にはいろいろな考え方や習慣があることを知り、さらに興味が深まりました。
私は将来、日本に住んでいる外国の子どもたちが安心して学べる塾を開きたいと思っています。言葉や文化のちがいで困っている子どもたちに、少しでも力になりたいです。そのためには、英語だけでなく、日本語やほかの教科の力も付けていくことが大切だと思っています。
学校では、友達と協力して活動することが好きです。話し合いの時間には、みんなの意見を聞いてまとめたり、自分の考えをわかりやすく話すように心がけています。時々、意見が合わないこともありますが、ちがう考えを知ることで、自分の考えも広がることがあると気付きました。
これからも、自分の興味を大切にして、いろいろなことにチャレンジしていきたいです。そして、友だちと協力しながら、少しずつ将来の夢に近づいていきたいと思っています。
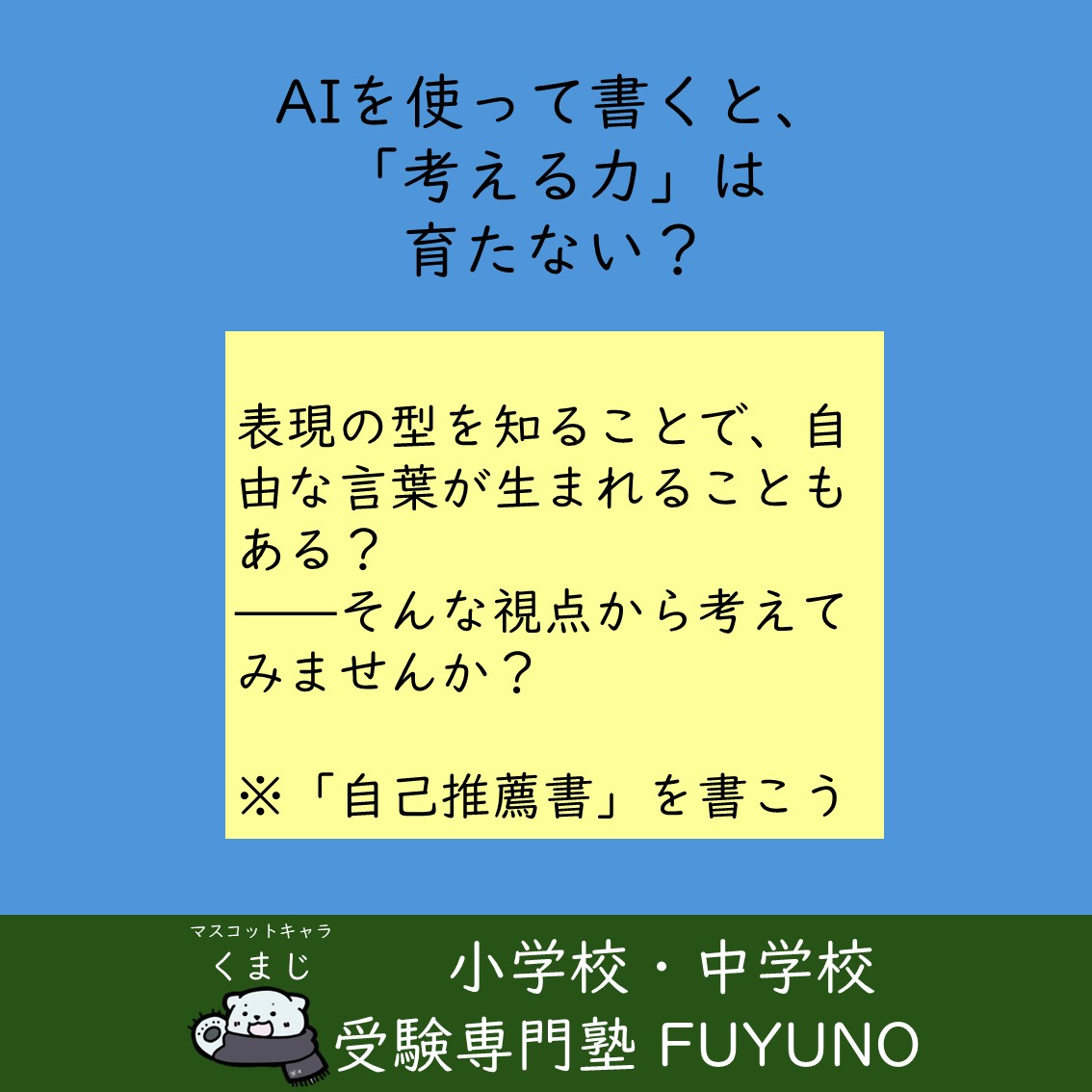
コメントを残す