「鉛筆折れた!」のあとに、何が続くといいんでしょう?
「だから新しいの貸してほしい」
「削ってもらえると助かる」
「どうしたらいいか分からない」
こんなふうに、“どうしてほしいか”まで言葉にできると、ぐっと伝わりやすくなります。
でも実際には、「鉛筆折れた!」で終わってしまうことが多いんですよね。
それは、子供が悪いわけじゃなくて、そういう言い方でも通じてしまう環境があるから。
大人が優しく察してくれると、言葉にしなくてもなんとかなる。
でもそれが続くと、「言わなくてもわかってもらえる」が当たり前になってしまいます。
すると、主語が抜けたり、気持ちが言えなかったり、「お願い」が言葉にならなかったり。
そしてもうひとつ、ちょっと気になるのが、「わかってくれないのが悪い」と思ってしまうこと。
本人は言っていないのに、相手が察してくれないと不満を感じる。
これが積み重なると、「伝えようとする努力」よりも「察してくれない相手が悪い」という、ちょっと他責的な思考が育ってしまうこともあるんです。
言葉にするって、ただ話すことじゃなくて、「自分の中にある思いを整理して、相手に伝えること」。
それは、国語力の土台であり、人との関係を築く力でもあります。
「鉛筆折れた!」のあとに、「だからどうしてほしいか」を言葉にする練習。
それが、子供の“伝える力”を育てる第一歩になるのかもしれません。もちろん、伝えてくれた時は満面の笑みで「わかったよ!ありがとう!」で返してあげたいですね。
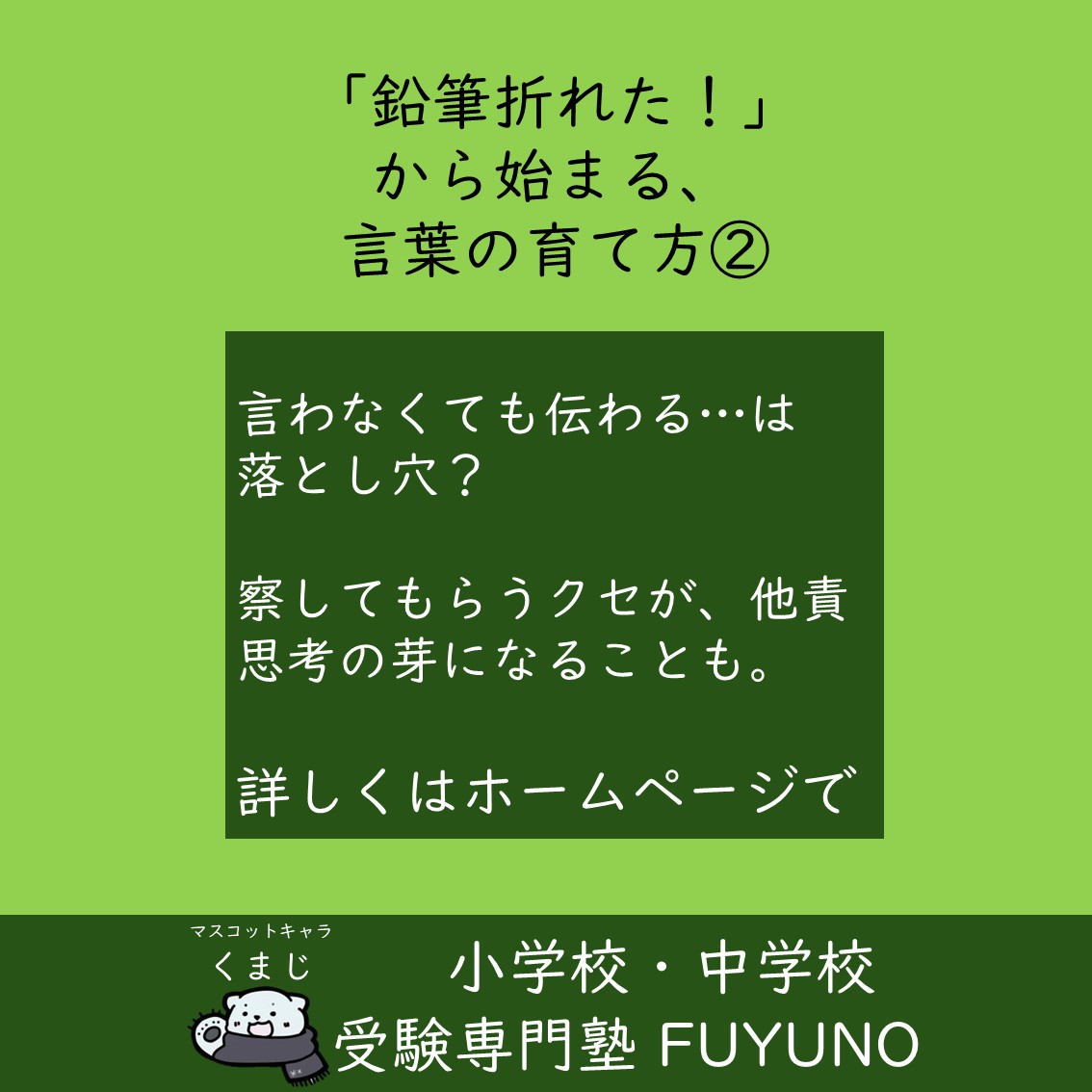
コメントを残す