「音楽の成績って、歌がうまいかどうかで決まるんじゃないの?」
そんなふうに思っている方は、少なくないかもしれません。けれど、実際の評価項目を見てみると、歌唱や演奏だけでなく、「鑑賞」の力も大きく関わってきます。
たとえば、ある授業では「この曲を聴いて感じたことを言葉で表そう」という課題が出されます。ここで求められるのは、音楽的な感性だけではありません。
「リズムが楽しい」「きれいな音だった」だけでは、評価は伸びません。
一方で、「軽快なリズムが心を弾ませるようで、まるで春の風のように感じた」など、豊かな語彙と比喩を使って表現できる子供は、より高い評価を受けます。
このように、音楽という一見“言葉”とは関係なさそうな教科でも、表現力が成績に影響するのです。
実はこの傾向は、音楽に限った話ではありません。国語や社会はもちろん、理科や算数でも、子供の「伝える力」が評価に直結する場面が増えています。
学校教育では、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「学びに向かう力・人間性」という三つの柱が重視されていますが、このうち「表現」は、見落とされがちな力です。
この連載では、各教科でどのように表現力が問われているのか、そしてその力が高まることでどんな変化が起きるのかを、具体的な場面を通して紹介していきます。
第1回では、学校の教育課程の中で、どんな場面で表現力が求められているのかを見ていきます。
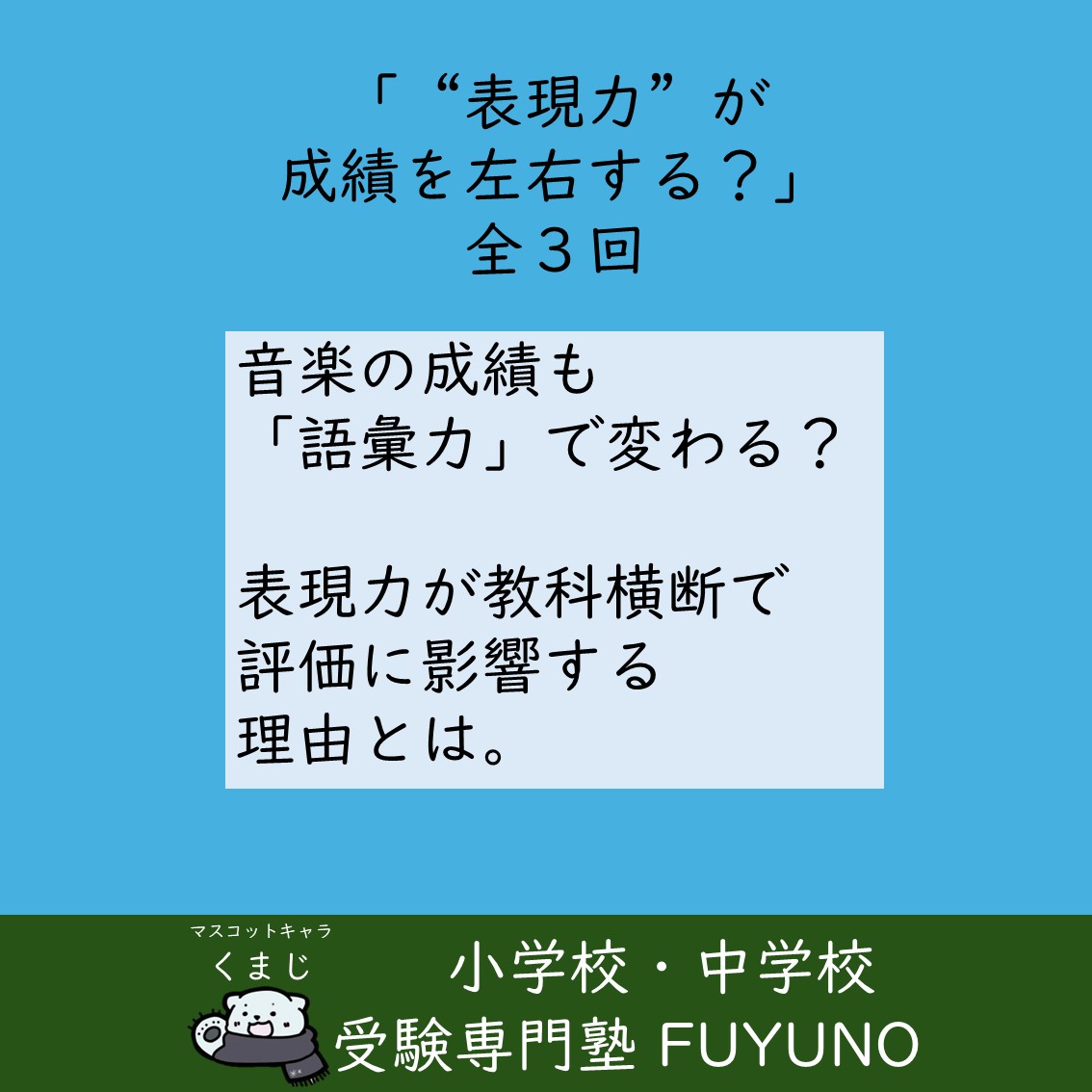
コメントを残す