「表現力」と聞くと、作文やスピーチのような“言葉を使う場面”だけを思い浮かべるかもしれません。けれど、実際の学校教育では、ほぼすべての教科で「表現」が評価の対象になっています。
文部科学省が示す学習指導要領でも、「思考・判断・表現」という観点が、子供の学びを支える柱とされています。このうち「表現」は、単なるアウトプットではなく、思考の深さや理解の確かさを伝える手段として位置づけられています。
学校教育では「思考・判断・表現」の三つの観点が重視されています。中でも「表現」は、教科を問わず評価に大きく関わる力です。以下に、各教科で表現力が問われる具体的な場面を紹介します。
🔍 各教科での「表現力」が問われる場面
国語
自分の考えを文章でまとめる記述問題
説明文や物語文の読解後の感想や意見の表現
社会
資料を読み取って意見を述べる活動
歴史や現代社会の出来事についての考察文
理科
実験結果の記録と考察の文章化
観察内容の説明や予想の根拠の提示
算数
文章題の解法の説明
図や式を使って考え方を伝える場面
音楽
鑑賞文での感想や印象の言語化
曲の特徴を比喩や感情を交えて表現する活動
図工(図画工作)
作品の意図や工夫を言葉で説明する場面
制作過程の振り返りや感想の記述
体育
運動の振り返りや目標設定の記述
チーム活動での作戦や役割分担の説明
このように、学校の教育課程の中では、教科を問わず「表現力」が求められる場面が数多く存在します。
次回は、こうした場面で「表現力が高い子供」がどんな表現をしているのか、具体的な例を通して見ていきます。
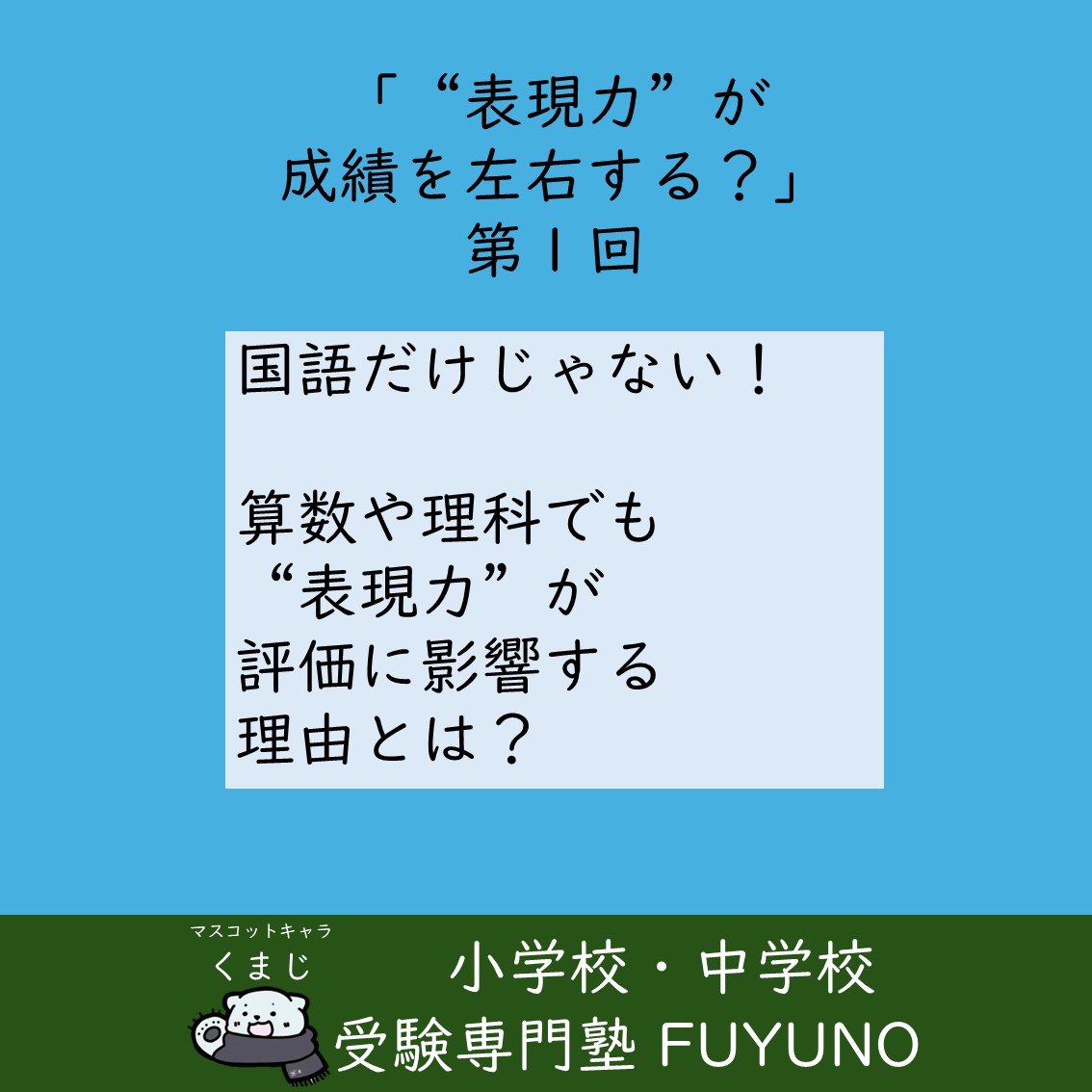
コメントを残す