子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、親としてはすぐにでも何かしてあげたくなります。「先生に話してみようか?」「友達のこと、聞いてみようか?」と動き出すのは、子どもを守りたいという気持ちの表れです。でも、少しだけ立ち止まってみることも大切です。
まず、子どもの話を聞いたあとに「私はあなたの話を聞いて、とても心配になった」と、自分の気持ちを伝えること。これは、子どもにとって「自分の言葉が親に影響を与えた」という実感につながります。そして、「だから先生に話してみようと思う」と続けることで、子どもはその先の展開を想像します。
このとき、子どもが「えっ、それは困る」と言う場合があります。もし本当に困っているなら、親が動いてくれることは安心につながるはずです。そうならない場合は、話の中に少し誇張や“演出”が含まれていた可能性もあるのです。
親が冷静に対応することで、子どもは自分の言葉を振り返るきっかけを得ます。「本当にそうだったかな?」「ちょっと言いすぎたかも」と、自分の気持ちを整理する時間が生まれます。これは、子どもが自分の感情と向き合う力を育てる大切なプロセスです。
また、親がすぐに第三者に責任を求めるのではなく、まず親子の間で話を整理することで、子どもは「自分のことをちゃんと見てくれている」と感じます。それが、安心感や信頼につながっていくのです。
子どもの不満に対して、すぐに動くことも時には必要です。でも、動く前に「どう伝えるか」「どう受け止めるか」を考えることで、親子の関係はより深まっていきます。
次回予告
最終回では、子どもの不満を聞くときに大切にしたい「関係性の視点」についてまとめます。
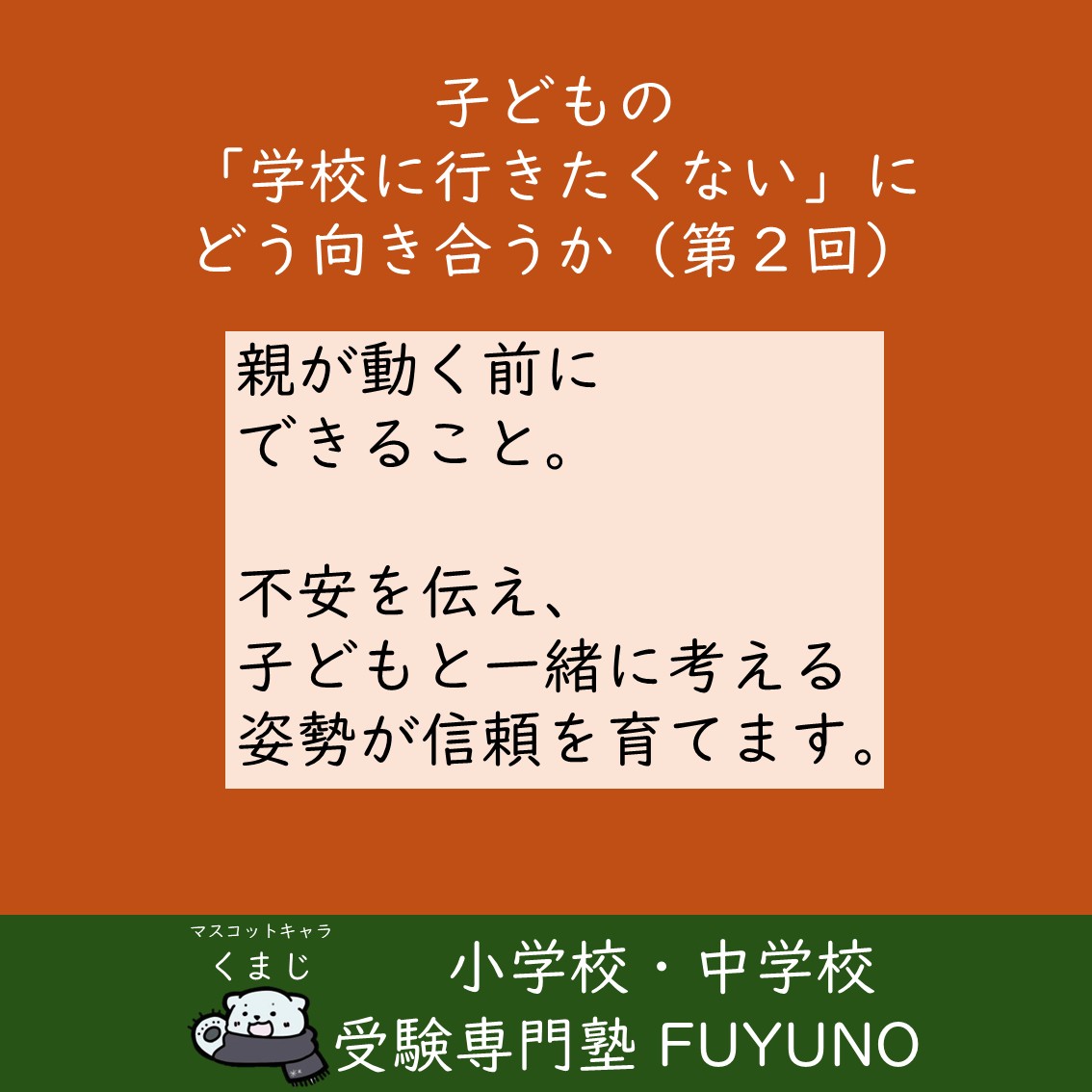
コメントを残す