前回、「小学校受験の願書の書き方」を(1)、(2)と2回に分けて書きました。では、「中学校受験の願書の書き方」はどうなるのでしょうか。
中学校受験の場合は、同じ「志望動機」でも、主語が変わってきます。つまり、保護者の志望動機ではなく、小学6年生のお子さんの志望動機を聞いているわけです。もちろん、大人の目で確認したり、手が加わることは大切ですから、最終的には大人の書いた分と違いなくなるのですが、多くのアドバイスには「親の代筆はダメ!」と書いてありますね。
そろそろこの辺りは、学校の意識改革に敏感になった方がよいです。夏休みの自由研究や宿題も、今や「親と一緒になって取り組むこと」が当たり前。それを見た先生方も「一緒になって課題に取り組んでいるいい家庭」と捉えることだってあります(さすがに全部が全部お膳立てする、代わりに作成してしまうのはやりすぎですが)。
つまり中学校にとっては、「親の代筆かわからない」ほど、子供が成長している方が大切なのです。小学校受験同様、面接等では志望動機に係ることを問われます。お子さんが、願書の内容を自分のものとして十分取り込むことができていれば、何ら問題はないわけです。それは、テンプレート文例を覚えるのとも、スムーズに答える練習をするのとは違います。自分の体験や思いとして、染みついているかが重要なのです。
これは、親が書く「子供の長所・短所」についても、同じことが言えます。ただ、中学校受験には親の面接はないことが多いので、小学校受験に比べると、まだ親の心配度は低くてよいかもしれませんね。
ということで、基本的なことは小学校の願書の書き方と変わりません。
「うちの子はこんなに良い事は書けないかも…」と不安にならなくて大丈夫です。ポイントはこれが、「今(4月)でも書ける」ということです。
というのは、今書けば「嘘・大げさ」になることも、面接の時までに「本当の体験」にしてしまえばよいのです。
当サイト:「小学校受験の願書」の書き方(2)より
「子供像」を各家庭でも、もっておくことが大事なのです。そうすれば、子供の成長は目に見えてわかりますし、もし上手くいかなくても「挑戦した」事実は変わりません。そして、面接官からは「こんな子供に育ってほしいというイメージをもって子育てをしている」という、「教育への考え方をもった親」と映ることでしょう。
当サイト:「小学校受験の願書」の書き方(2)より
FUYUNOに入塾いただければ、「6月中に」こちらからいくつかの願書をお示しした上で、みなさんのご家庭やお子さんに近いものをお選びいただきます。その後は、それに対してどう育ってきたかを継続的に確認しながら、受験時の願書提出・面接指導まで行ってまいります。
きっと面接当日には、「本当に起きたことを」「自然体で」「必要以上に緊張することなく」面接に挑めることでしょう。
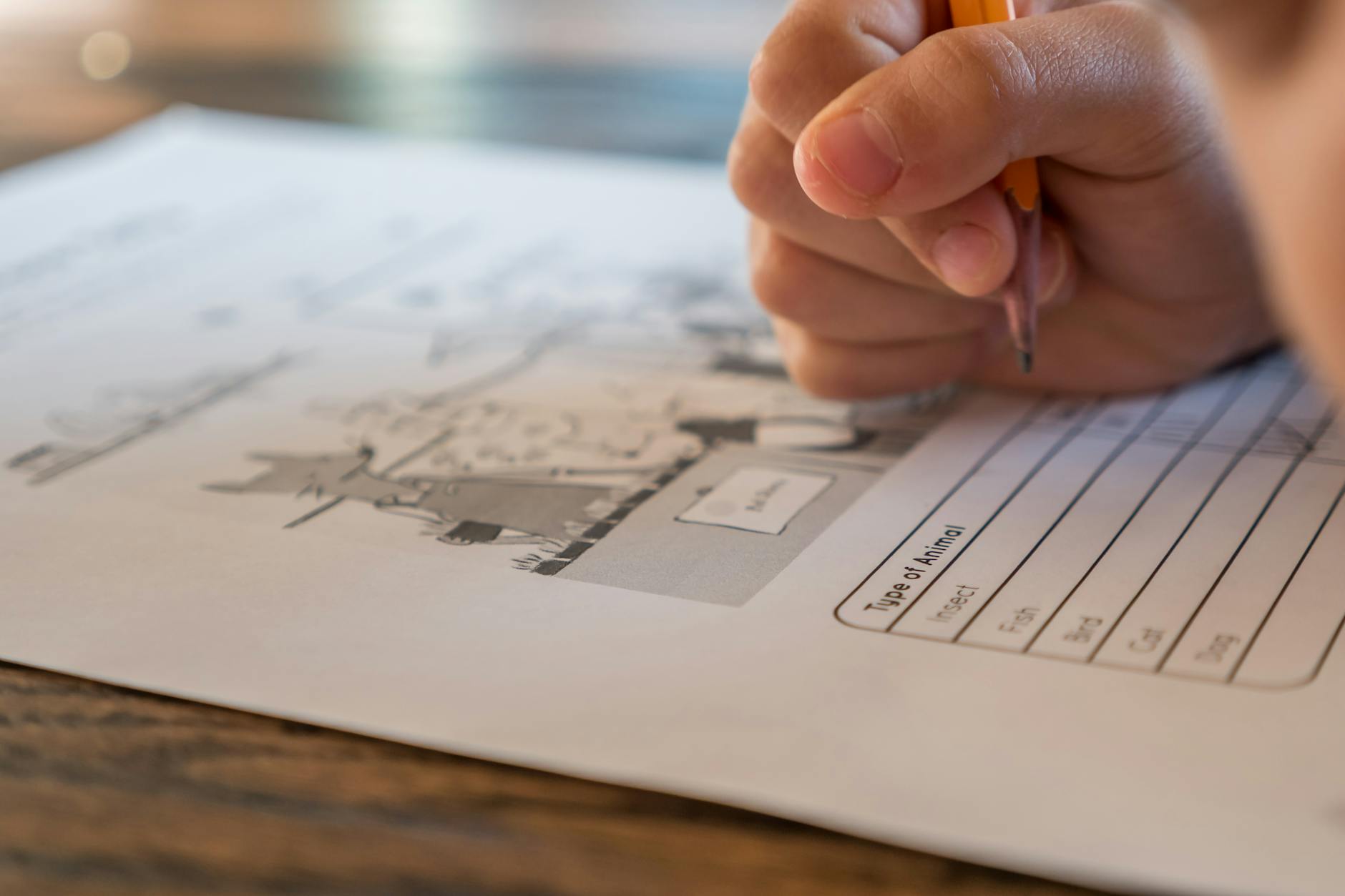
コメントを残す