「合わせて」という言葉が出てきたら、足し算。
この教え方、実はとてもよく見かけます。文章題の中に「合わせて」という言葉があると、すぐに「足し算だ!」と式を立てる。そんな場面、学校でも塾でも、日常的にあります。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみたいのです。
「合わせて」があるから足し算、というのは立式の意味ではある程度正しくても、本当にその方法でよいのでしょうか?
実はこの教え方には、大きな落とし穴があります。
それは、「場面を想像する」という大切なステップを飛ばしてしまうこと。文章題は、ただの言葉ではなく、状況を読み取る力が求められます。ところが、「合わせて=足し算」とだけ覚えてしまうと、子供たちはその場面がどんな状況なのかを考えずに、機械的に式を立ててしまうのです。
たとえば、「5個のりんごと3個のみかんを合わせて」と言われたとき、本来は「りんごとみかんを一緒にする(同じ「くだもの」と捉える)と、全部で何個になるのかな?」とイメージすることが大切です。ところが、「合わせて=足し算」とだけ覚えてしまうと、「りんごとみかんを合わせるってどういうこと?」という問いが抜け落ちてしまいます。
もちろん、低学年の初期段階では、「合わせて」が足し算になる言葉だと教えることは、理解の助けになることもあります。ですが、ある程度の習熟が進んだ後も、言葉だけで判断してしまうと、文章題の本質にたどり着けなくなってしまうのです。
次回は、この「合わせて=足し算」という教え方が、なぜ広まったのか。そして、初期指導としての意味について、もう少し深く掘り下げてみたいと思います。
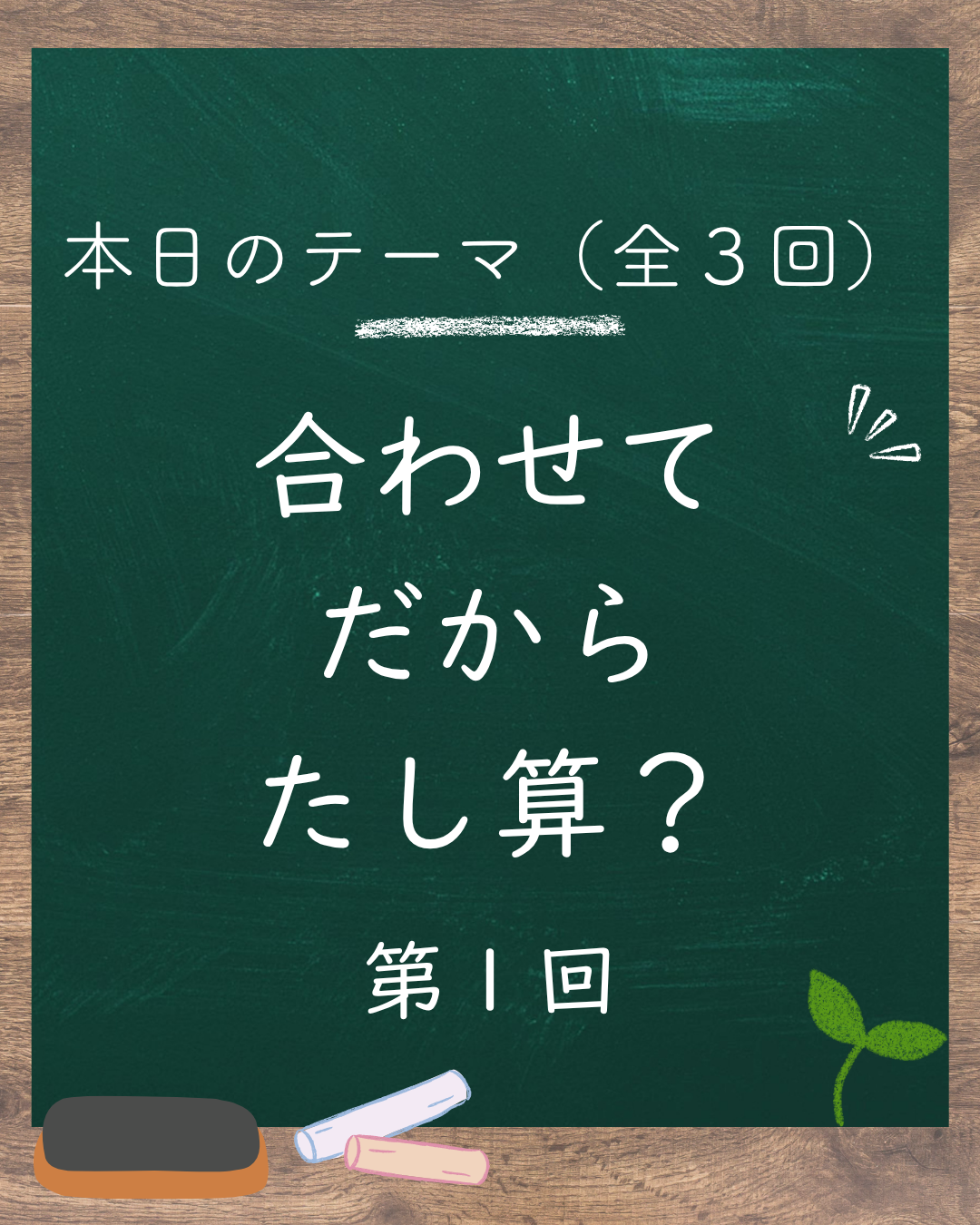
コメントを残す