「合わせて」があるから足し算。
この教え方が広まった背景には、「子供の理解を助けたい」という思いがあります。
算数の学習が始まったばかりの頃、子供たちはまだ「何をどうすればいいのか」がわかりません。そんなとき、「足し算になる言葉」として「合わせて」を教えることで、式を立てるヒントを与える。これは、初期指導としてはとても有効な方法です。
たとえば、「5個と3個を合わせていくつ?」という問題。
このとき、「合わせて=足し算」と教えることで、子供は「5+3」と式を立てることができます。これは、言葉の意味の理解がまだ追いつかない子供にとって、表面上の言葉を借りたサポートになります。
ただし、ここで大切なのは、この教え方は“補助”であるということ。
習熟が進んだ後も、「合わせて」があるから足し算、とだけ覚えてしまうと、文章題の本質を見失ってしまいます。文章題は、場面を理解して式を立てる力を育てるもの。言葉だけで判断するのではなく、「何がどうなっているのか」を考える力が必要です。
「合わせて」という言葉は、場面の中で意味を持ちます。
それが「何と何を合わせるのか」「どこでどう合わせるのか」など、状況を想像する力が育っていないと、式はただの記号になってしまいます。
次回は、そんな「合わせる」場面をどうやって子供に伝えるか。
言葉だけでなく、動きや視覚的な情報を使って、子供が「合わせる」イメージを持てるようにする方法を考えていきます。
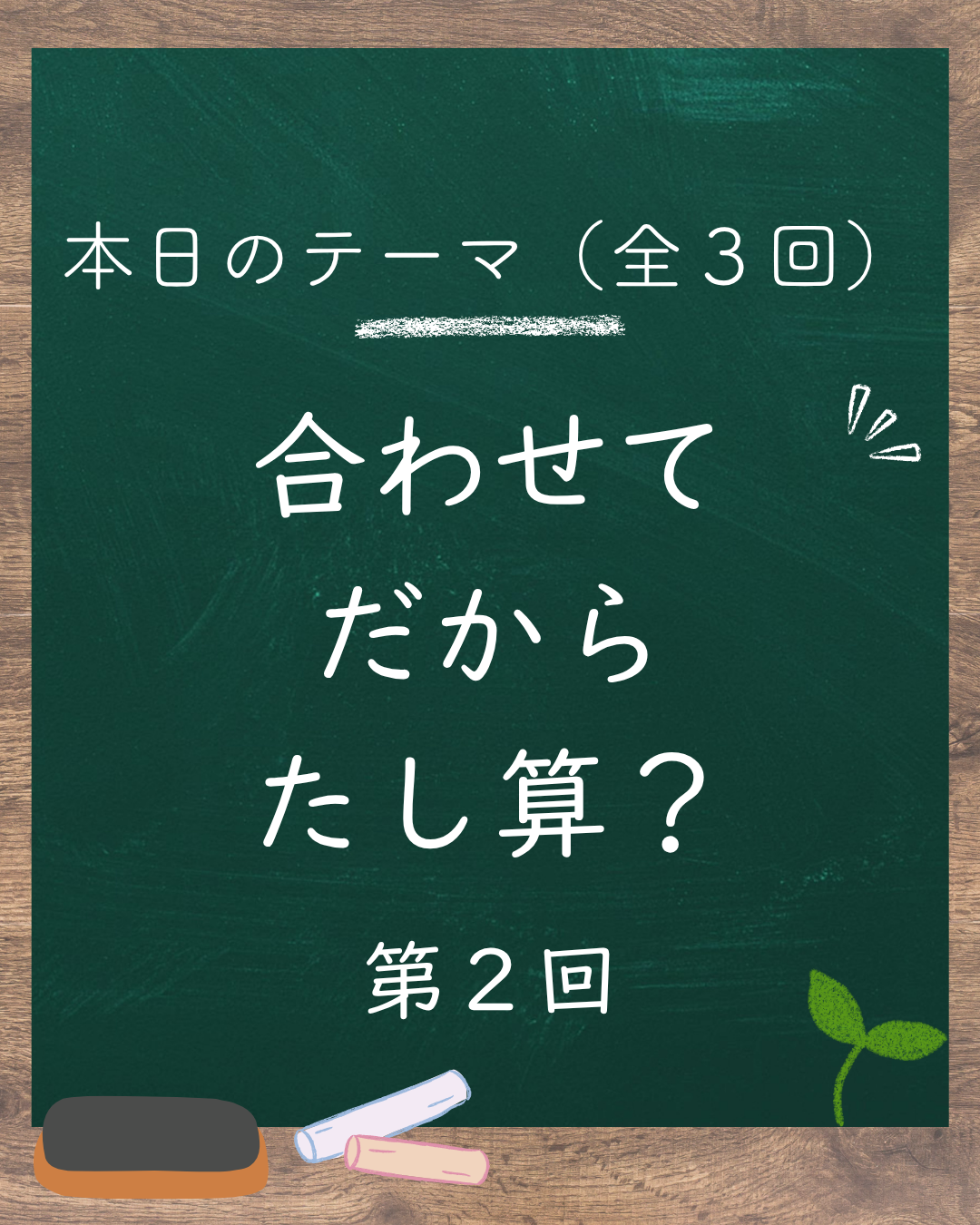
コメントを残す