国語のテストに係る考察をしていきます。ここでは、漢字や語句のような語彙に関する問題ではなく、読解問題についての考察を中心に進めます。今回は②です。
①授業とテストの乖離
②テストの問題の類型
③テストで問われる資質・能力
④点数が取れない子供の傾向
⑤当塾における現状の対策
⑥今後必要となる取組
さて、「国語のテスト対策」を行う前に、「国語のテストの問題」にはどのようなものがあるか、について整理します。
まず、国語の問題は大きく分けて以下2つの部分が存在します。
A:聞いている内容
B:答え方の指定
Aについては、例えば「下線部の『それ』がさすものは何でしょう。」のような、「問題」のことです。これはイメージしやすいでしょう。解答者はこの問題の答えとなる部分を、問題文中から探すことになります。(この部分の詳細は③で詳しく考察します)
特にAの問題の多くは
A-1 「『(それ・これ・あれ・どれ)』とは何か」(指示語説明)
A-2 「○○したのはなぜか」(理由・根拠の説明)
A-3 「○○とは(何・いつ・だれ)か」(状況の説明)
の3つがほとんどです。そしてそれは、自分の頭で考えるのではなく、該当箇所を探す(必要に応じて整理する)ことで答えられます。
Bについては、例えばAの問題の後に付く「(指示語が示すものを)三文字で書き抜きましょう」「(当てはまる一文を探し)最初の五文字を書きぬきましょう」のような、「答えの書き方」のことです。これは授業中には全く扱わない内容です。学習指導要領にも「何年生から学ぶ」のような指定は無く、授業中に「答え方」について学ぶ機会はほとんどありません。
では、「国語のテスト対策」が必要な子供にとって、より難しいのはA,Bどちらなのでしょうか。そして、どちらの方がより難しいと捉えられがちなのでしょうか。そのあたりを「③テストで問われる資質・能力」で考察します。
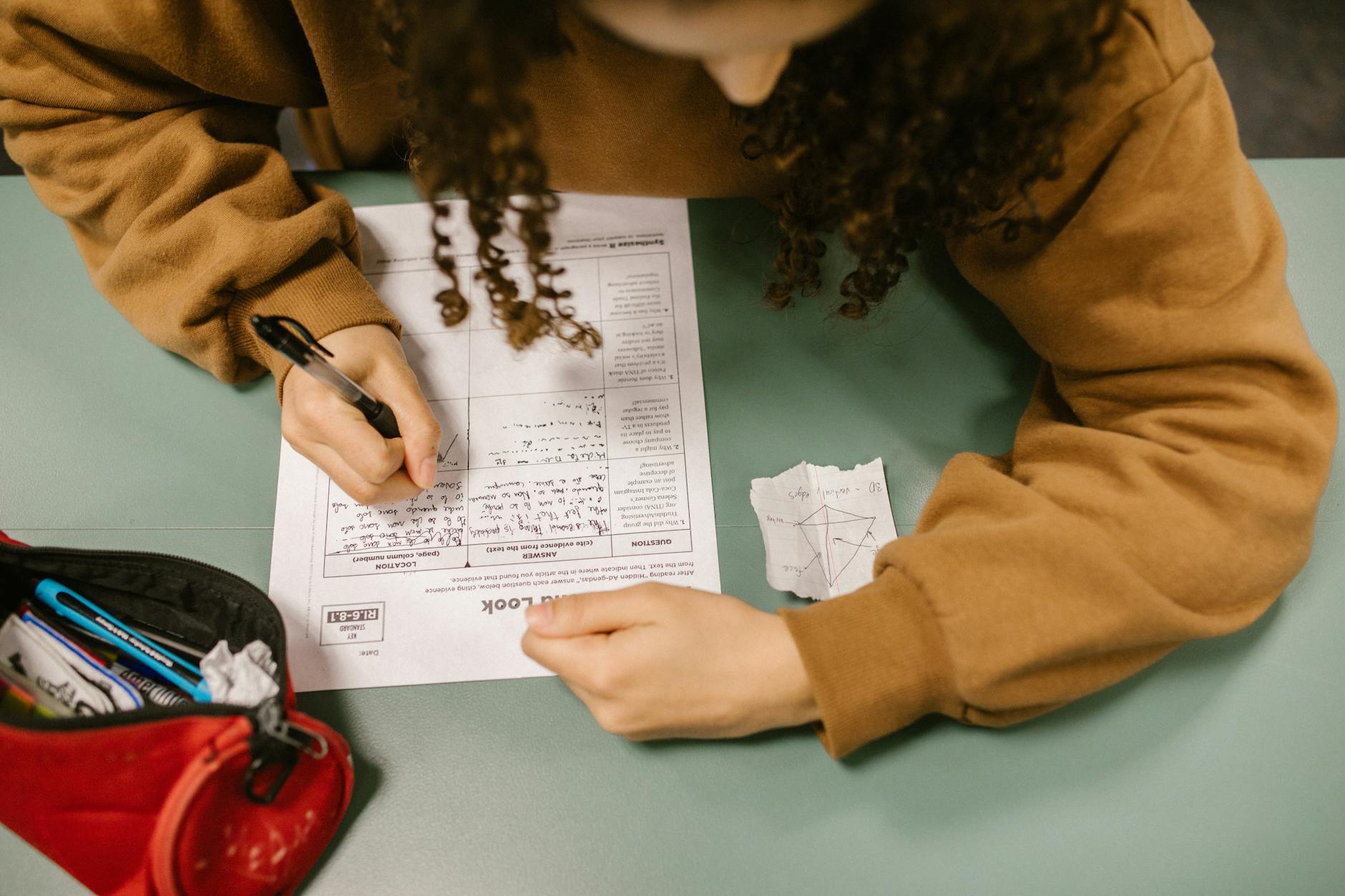
コメントを残す